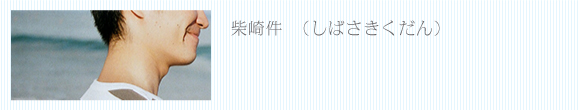![]()

2013.08.06
第十四話 「擬似回帰」
【 7/28 SUN PM 00:07 】
タンノはデスクに置かれたカレンダー付きの時計を見る。
これはいつだ?
これは現実か?
大きな呼吸をゆっくりと繰り返して少しずつ鼓動を落ち着かせていった。
胸に手を当てると、汗で湿ったシャツの奥に、確かに心臓が動いていた。
俺は生きている。
呼吸もしているし血も流れている。
虚の空間だろうが擬似の世界だろうが、俺は生き返ったのだ。
悪い夢から解放されたように、安心感が腹の底から滲むように伝わってくる。タンノは椅子に深く腰を下ろし、安堵のしるしとしてため息を一つ吐いた。
手の指先や足は、まだ細かく震えていた。
机の上には作業途中の書類があった。英語とフランス語で印刷された文章に、青と赤のペンで細かい文字が書かれている。その文字はタンノのものだった。
そうだ、俺はこれを覚えている。
今日は日曜日。
回ってくるはずの原稿が押しまくって、休日に出勤しなければならなかったのだ。
そして、俺はその作業をしていた。
そうだ、覚えている、思い出せる。
タンノは目の前の世界と記憶をひとつずつ照らし合わせて確認した。
タンノは海外の書籍をメインに取り扱う出版会社に勤めており、その中の翻訳部門に配属されていた。しかし、翻訳部門というのも名前だけで、実際の仕事は翻訳だけでなく、記事の編集や校正、作家や他の出版社とのやりとりなど、人手が足りない場合などは様々な業務が回ってきた。
タンノはその日、フィンランドの家具を紹介する雑誌の短い紹介文の書き起こしと、数本の原稿の翻訳をしていた。週末までに送られてくるはずだった原稿が日曜の朝方に届き、その作業をするために出勤していたのだ。
そうだ、だから誰もいないのだ。
窓の外に揺れる薄い緑の葉を見ながらタンノは思った。
閉め切った窓の向こうから、車の走る音と横断歩道の信号機の補助音と、分厚く重なった蝉の声が聞こえてくる。
強烈な太陽の光が緑の葉をつらぬいて、落ちる影さえもかき消してしまいそうだった。
すべてが夢だったように、ぼんやりと思い出しながら外の光を眺めていると、腹が小さく鳴った。
空腹につつかれるようにして、記憶が呼び起こされる。
この空腹も覚えている。
確か、この後……。
暗い水の中に沈んだ記憶を手探りで探すようにして、目を閉じた。
記憶の輪郭に指が揺れた時、男の声がした。
「タンノ君」
部署を仕切るパーテーションから男が顔を覗かせる。
タンノは突然の登場に驚いて身を固くした。
「片桐さん、いたんですか」
姿を見せたのはタンノの先輩である、片桐という男だった。
タンノが入社した頃、片桐は同じ翻訳部署で働いていた。それからしばらくして、片桐は別の部署に異動になってしまうが、その後も仕事の合間に食事をしたり、仕事の終わりに酒を飲みに行ったりした。
タンノが会社の中で個人的に付き合いがある、数少ない人物の一人だった。
この驚きも記憶にある、とタンノは思った。
「どうした? 顔色おかしいぞ、体調悪いのか?」
「そうですか? 別に、体調は大丈夫ですけど」
タンノは頬に手をあてて言う。
そうか、と片桐は返した。
「ごはん行くけど、一緒に行かないか?」
「ああ、いいですね、ちょうど腹減ってたんで。どこ行きます?」
「『しなの屋』でハムカツ定食」
「いつものですか」
「そう、いつもの」
片桐はそう言って、子供が笑うみたいに嬉しそうに笑ってみせた。
片桐はタンノより年が五つ以上も上で三十代の後半になる男だったが、時折、その年齢と体格に似合わない少年のような無防備な笑顔を見せた。
記憶の通りだ、とタンノは思う。
「でも『しなの屋』は今日、休みですよ」
「なんでよ? いつも日曜はやってるだろう、あそこ」
「今日は臨時休業です。ガスだか水道だかの工事で」
「噓だろ、なんで知ってるのよ?」
「知ってるんです、別に店まで行ってみてもいいですけど」
「うん行く。だって食べたいもんハムカツ定食」
「やってなかったら、『やすをか』がいいです。『やすをか』の豚ショウガ焼き定食」
「別にどこでもいいけど、とりあえず、『しなの屋』行ってみてからだな」
「わかりました。ちょっと用意するんで、下で待っててください」
タンノがそう言うと、オーケーと言って片桐は去っていった。
呼吸が浅くなり、タンノの指先が再び震え始めた。
俺はこの後、刺されるのだ。
(続)
![]()
![]()
![]()
![]()
 恋するクレヨン 2013.07.15
恋するクレヨン 2013.07.15 musiquoとmusiquo musiqua 2013.08.09
musiquoとmusiquo musiqua 2013.08.09 miscorner/c+llooqtortion ミスコ-ナ-ル-クト-ション 2013.08.23
miscorner/c+llooqtortion ミスコ-ナ-ル-クト-ション 2013.08.23 だし、みこし、おおだいこ。 2013.09.12
だし、みこし、おおだいこ。 2013.09.12 「空白連鎖」書籍篇(文学フリマサンプル) 2013.10.30
「空白連鎖」書籍篇(文学フリマサンプル) 2013.10.30