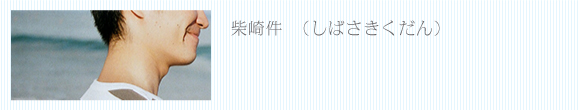![]()

2013.10.30
「空白連鎖」書籍篇(文学フリマサンプル)
11月4日の文学フリマで販売する書籍の一部です。
ウェブで掲載している「空白連鎖」とは別の世界です。
でも、タンノさんは相変わらず大変です。
—————————————
(一)
光が瞼の裏側で点滅して、タンノは目を覚ました。
眉間にしわを寄せて薄く開いた目に、睫毛で拡散した輝きが差し込む。電車の窓は一面、黄金に輝いていた。電柱や木が窓を横切る度、不規則な信号を送るみたいに、光が点滅する。
タンノは、電車が今どのあたりを走っているのか確認しようとしたが、光によって車内の案内表示は見えなくなっていた。しばらく目を凝らしていたが、やがて諦めて床に目をやった。窓の影が瞬きをするみたいに点滅しながら、ゆっくりと形を変えている。どこらへんだろう、とタンノは豪快なあくびをして思う。
不完全な眠りと飽和した光のせいで、タンノの思考はうまく働いていなかった。電車の車両にはタンノの他に乗客はいなかった。乗り込んだ時にはいくらか人が乗っていたが、眠ったり目覚めたりを繰り返して都心から離れていくうちに、客は徐々に少なくなっていった。窓の外にあったビルやマンションなどの建物も消えて、手の付けられていない緑と古びた住宅しか見えなくなっていた。
平日の昼間で、本来であればタンノも他のほとんどの人と同じように仕事をしている時間だった。しかし、この日は違っていた。やりたくなかったのだ。やりたくなくなってしまった理由はいくつかあるが、その全てが気分の悪いものだった。
自分はこれ以上、この仕事に関わりたくない。
タンノはそれだけを言い残してこの電車に乗った。聞いた事のない終点の駅まで行く電車を選んで、空いている車両の座席の端に座り、目を閉じた。
どれくらい乗っただろう? 一時間か、一時間半か、二時間か。
座り続けているせいで体は痛いし、溢れかえる太陽の光のせいで頭も少し痛かった。タンノは車両に人がいないことを確認してから立ち上がって、大きく伸びをした。固まった筋肉が抵抗するみたいに痛みを放つ。路線図を確認しようとしたが、少し考えてから思い直して、また座席の端に腰を下ろした。
別に、今がどこでもいいか。でも、もう少ししたら帰ろう。帰って何か、別の事をしよう。
タンノはいつの間にか慣れてしまった光を眺めた。
誰もいない電車はいい。
そう思いながら再び目を閉じて、心地良い揺れに身を任せた。
(二)
車両のドアが開く音で、タンノの浅い眠りが途切れる。
歯切れの悪いアナウンスのせいで駅の名前がわからなかったが、タンノはとりわけて気にはしなかった。
ドアは開いたが乗る客も降りる客もおらず、辺りはひっそりとしていた。気まずい沈黙をやり過ごすように、ホームも車両も白々しく佇んでいた。車両の軋む音だけが、虫が鳴くみたいに聴こえてきた。
開いたドアからは山がのぞいていた。遠くの方で、聴き覚えのあるノイズが鳴っているのにタンノは気付いた。
海の音だ、とタンノは思う。しかし、目に見えるのは薄い緑の山々とささやかな住宅だけで、海がありそうな雰囲気はなかった。
風の音がそのように聴こえたのかもしれない。タンノはそう思いながら、座席の横についた手すりの棒に頭を預けた。
ドアが閉まって電車が動き出すまでの間に、ほんのわずかな静寂が生まれる。その静寂を壊すように、すぐ隣から、ねえ、という声がした。タンノは驚き、小さい悲鳴を上げて振り向く。こじんまりとした瞳と目が合った。
さっきまでいなかったはずの少女が足を揺らして座っている。
「なに?」
タンノは急発進した心臓の鼓動を隠すように、最小限の返事をした。
「これ」
少女はそう言って、タンノのズボンのポケットから垂れている携帯電話のストラップを指さした。ストラップはあるアニメのキャラクターのフィギュアだった。
「これ、ロンロンでしょう?」
「ロンロン?」
「この子、ロンロンじゃないの?」
少女は首を大げさにかしげてタンノに訊く。短い前髪が日に焼けた額にぱさぱさと揺れる。
少女の指差すストラップは、タンノが最近友人になった人物からもらったもので、その友人は、友人になる前は恋人だった。
ストラップのフィギュアは「コッコちゃん」という、彼女が好きなキャラクターだった。コッコちゃんは猫とクラゲを融合させた不思議な生き物で、猫の爪やクラゲの毒で敵を倒したり、透明になる能力や素早い身のこなしで事件を解決するアニメの主人公だった。タンノ自身はそのアニメについてそれほど興味はなかったが、彼女の影響でそのキャラクターだけは気に入っていた。
「これはロンロンじゃないよ、コッコちゃんって言うんだ」
タンノがストラップを指でつついて言うと、少女は口を尖らせた。
「コッコちゃんて、なにそれ、変な名前。絶対ロンロンだよ。コッコちゃんなんて、聞いたことないもん」
「じゃあ見てごらん」
タンノはそう言ってフィギュアの足の裏を少女に見せた。そこにはアニメのロゴである「怪傑!コッコちゃん」の文字の印刷がされているはずだった。
「ほら、やっぱりロンロンだよ」
少女は噓を見破ったように得意気に言う。そこに印刷されていたのは「怪傑!コッコちゃん」ではなく「名探偵ロンロン」の文字だった。タンノは目を疑い、指でその印刷をなぞった。
おかしい。これは何年も前からコッコちゃんだったはずだ。アニメも何回か見た事があるけど、ロンロンなんて聞いたことがない。いつの間にか、誰かにすり替えられてしまったのだろうか。
「ほんとだ、ロンロンだ」
タンノは呆然として言う。少女の揺れる足が催眠術の振り子みたいに見えてくる。
「ね、ロンロンでしょ」
かわいい、と言いながら、少女はフィギュアを弄り始めた。いつまで持っているのだろう、とタンノは揺れ続ける少女の膝やすねを眺めて思った。
いつまで持っているのだろう、もう別れてから三ヶ月も経つ恋人からの些細なプレゼントを。捨ててしまえばいいのに、でも、捨てるタイミングなんてどこにもなかった。こういう所がダメだったのかもしれない。きっと、ストラップごときどうでもいいと思えているから、いつまでもぷらぷらとつけていられるのだ。どうでもいいと思っていなければ、ちゃんと処理をしているはずなのだ。俺は彼女の事を、彼女がくれた物を、どうでもいいと思っていたのだろうか。少なくとも、大切にはしていなかったのだろう。だから、いなくなったのだ。もっと大切にしてやれていれば、いなくなる事もなかったのに。
三ヶ月前から繰り返し考えている事が、タンノの頭の中で再び読み上げられる。都合の良い自虐と後悔の痛みが、鎖骨のあたりを絞るように刺激する。
ストラップを弄る少女の腕に、タンノの涙が落ちた。少女は驚いてタンノを見る。
「どうしたの? 大丈夫? どこか痛いの?」
タンノは抑えられないまま、涙を流し続けた。手で顔を覆い、だいじょうぶ、とだけ言った後、声を出さずに泣き続けた。
遠ざかっていた電車の走る音が、心配するみたいに近づいてくる。少女はタンノの隣で何も言わず、静かに足を揺らしていた。
次の駅のアナウンスが鳴る。ゴウダノとかコウザノとかいう名前が耳に入る。降りよう、とタンノは思う。
シャツの袖を引っ張って涙を拭い、少女の方を見た。少女は眉を落としたまま、心配そうな顔でタンノと目を合わせた。
「いる?」
タンノは指でストラップをつつきながら言う。
「くれるの? 大事なものじゃないの?」
大事なものじゃないの? と、タンノは頭の中で少女の言葉を繰り返した。
「大事なものだけど、大事にできなかったものなんだ」
そう言って、タンノはストラップを外して少女に渡した。少女は不安そうな顔をしていたが、やがて笑顔を作って、ありがとう、と言った。
電車が駅に近づいてきた時、車両の連結のドアが勢い良く開き、中年の女が突進するように向かって来た。
「さなえ、なにやってるの、もう降りるわよ!」
女は少女の母親らしく、少女の腕を乱暴に引っ張り上げた。少女の手からフィギュアが落下する。
「何やってんの、そんなものどこで……」
母親はそう言ってタンノを見た。顔に残った泣き跡を見て気味悪がってか、彼女は無言で視線を逸らし、少女を連れて隣の車両へと戻っていった。
母親が登場してから去るまで、少女とタンノは何を言う隙もなく、去り際にほんの少し目を合わせただけだった。連結のドアが閉まるとタンノは置き去りにされた気持ちになった。床に転がったフィギュアを眺めているうちに、電車が駅に停まってドアが開く。
フィギュアを拾おうか迷っていると、発車のベルが鳴り出した。追い立てられるようにフィギュアを拾い上げて、タンノは電車を降りる。
拾わなければいいのに、こういうところがダメなんだ。
そう思いながら、タンノはフィギュアをズボンのポケットに突っ込んだ。
電車が走り出す。誰もいなくなった車両の中で、光はまた点滅を始めた。
書籍に続く…。
(ブースはB-33です)
![]()
![]()
![]()
![]()
 GRAPEVINE 「1977」 2013.06.22
GRAPEVINE 「1977」 2013.06.22 いくえみ綾 「私がいてもいなくても」(1) 2013.06.27
いくえみ綾 「私がいてもいなくても」(1) 2013.06.27 スチルボール 2013.07.18
スチルボール 2013.07.18 ジャスミン茶漬け 2013.07.16
ジャスミン茶漬け 2013.07.16 すずむしの鳴く宇宙で 2013.08.12
すずむしの鳴く宇宙で 2013.08.12