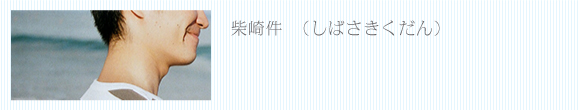![]()

2013.08.09
第十五話 「記憶と推測」
タンノは椅子に座ったまま、震える指先を見ていた。
大丈夫だ、刺されるまでにはまだ時間はある。
そして、記憶の通りなら回避する策はいくらでもあるはずだ。
何度か、大丈夫だ、と心の中で言ってから、震える手のひらを握って立ち上がった。
エレベーターで地上階まで下り、ロビーで待つ片桐に手を上げた。
自動ドアが開くと充満した熱気と湿っぽい街の音が二人にはりつく。
「かぁ、あっちいな」
片桐が手で日差しを遮って言う。
「あっちいですね」
タンノは目を細めて空を見る。
張り付くような熱気に包まれながらも、タンノの内臓は寒気を感じていた。溶けない氷が体中に散らばってるみたいな気がして、力を抜くと全身が震え出しそうだった。
灼けたアスファルトを歩くと何かをノックするような靴音が鳴る。暑さのせいか恐怖のせいか、視界が少しずつ白くなって、倒れてしまいそうだった。
前を歩く片桐が独り言のように何かを話しているが、タンノにその内容は聞こえていなかった。
「ほんとだ」
『しなの屋』の前で立ち止まり、下ろされたシャッターを見て片桐が言う。張り紙には、水漏れによる水道工事で急遽休む、という事が書いてあった。
『やすをか』だな、と片桐が言い、そうですね、とタンノが言った。
「ちゃんと食べてるのか?」
ヒレカツ定食をつつきながら片桐が言う。
日曜だったが席は七割ほど埋まっており、ノイズみたいなテレビの音と厨房で響く鍋の音と遠慮のない客の声で、店内はにぎわっていた。エアコンはついていたが、店の熱気でほとんど効果はなかった。
油まみれになった扇風機が、鬱陶しい空気を弱々しくかき混ぜている。
「食べてますよ、バッチリです」
倒れてしまいそうだったタンノの身体は、豚ショウガ焼き定食によって立て直された。
油で照り返る焼きたての香ばしい豚肉を口に運ぶごとに、タンノの気持ちはあっけなく落ち着いていった。
食べ物の力は偉大だ、とタンノは思う。
「なんか痩せたように見えるけど、気のせいか」
「夏だからじゃないですかね。動くだけで汗かきますし体力も消耗しちゃうんで、自然と痩せていってるのかもしれないです」
「そういうもんか? 俺なんかどの季節でも、何一つ変わらないけどな」
片桐はそう言って、少し出っぱった腹をぽんと叩いてみせた。
「それは単純に食べ過ぎですよ」
そう言ってタンノは笑った。
食べ終わってしまうと、心の中にあったはずの恐怖がすっかりと姿をなくしていた。一時的に忘れてしまっているだけなのだろうが、すべての不幸は空腹が原因なのではないかと思うほど、満たされた胃袋はタンノにやすらぎをもたらした。
刺された事も、あの白い世界も、すべてが夢だったように思えた。
だって、現実はもうここにあるじゃないか。そうだ、確かあの医者も言っていた。
現実はつじつまが合っているだけで、それが噓か本当かはあまり重要ではない、と。
確かにそうだ。この世界が噓だとしたら、目の前に座ってる片桐さんも本当は存在していないということになる。でも今、実際に目の前に存在しているのだ。これが現実でなかったら、何を信じればいいんだ?
俺はこの現実で生きる、この現実で生きていくんだ。
死ぬわけにはいかないのだ。
「どうした? 大丈夫か?」
片桐の声でタンノは我に返った。
「すみません、大丈夫です。ちょっと考え事しちゃってて」
タンノはそう言って、コップの水を一息で飲んだ。
「タンノ君、何か変だぞ、なんかあったんじゃないのか?」
タンノは視線を落として自分の指先を見た。
「ちょっと、悪い夢を見てしまって、それのせいかもしれません」
「どんな夢だよ?」
「刺されて死んで、天国か地獄かもわからないような場所にいく夢です。それが、どこまでが夢でどこからが現実なのかわからなくて、ちょっと思い出しちゃったりしてました」
「刺される夢か、そりゃ恐いね」
「いえ、刺されたのは、もしかしたら夢じゃないかもしれないんです」
「どういう事だよ? だって、今刺されてないじゃんか。刺されてたらこんなところにいないだろ」
「はい、ほんとにその通りなんですけど……」
タンノは今までの出来事について、どのように話せばいいか迷った。
虚の住人である片桐に何を説明するべきか、空になったコップを指でこつこつと叩きながら考える。
コップに張り付いた水滴をしばらく眺めた後、タンノは口を開いた。
「俺が刺されるのは、この後なんです」
(続)
![]()
![]()
![]()
![]()
 ハナエ 「変幻ジーザス」 2013.09.13
ハナエ 「変幻ジーザス」 2013.09.13 aus 「Closed」「Opened」 2013.07.18
aus 「Closed」「Opened」 2013.07.18 GRAPEVINE 「1977」 2013.06.22
GRAPEVINE 「1977」 2013.06.22 雨 2014.03.03
雨 2014.03.03 鉄の結晶 2013.08.11
鉄の結晶 2013.08.11