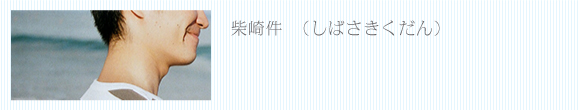![]()

2013.07.09
第六話 「水平線」
体が白い水に包まれた時、タンノは自分が何も着ていないことに気がついた。
川は足がつかないほど深く、タンノの体はいとも簡単に押し流されていった。犬かきに近いクロールで水をかき分け、水面に顔を出して空気を取り込む。
流されてしまったためか、目をやった対岸には真由美の姿は見えなくなっていた。
これは無理だ。
生き物の体液のような鈍く重い水をかき分けながら、タンノはそう思った。
もともと泳ぎは得意ではないし、こんな流れでは競泳の選手であっても辿り着くのは不可能だろう。それでも、タンノは腕を回して水をかき、足で蹴り続けた。死ぬために必死になるなんて滑稽だ、と頭の中でぼやきながら。
徐々に乱れてくる呼吸のなかで、もしかしたら、とタンノは気付く。
これが現実的な世界でなければ、呼吸をする必要はないのではないか。
試しに水中に潜ったまま呼吸を我慢してみた。
息がもたなくなると苦しくなってきたが、どうせほとんど死んでる状態なのだ、と半ば自棄になって無理矢理に耐えた。やがて限界がくるとタンノは肺のなかの空気をすべて吐き出してしまい、白い水がごくごくと喉に入ってきた。必死にもがいて水面に上がろうとするが、水流はタンノを深い場所まで運んでいった。
苦しさが極限まで達したとき、感覚が消えたようにふっと楽になった。
違う場所に運ばれるような感覚があったが、しぼっていた目を開けてみても視界は白いままだった。まだ川の中にいるのだ。肺にまで白い水が溜まって、自分も川の一部になったようだった。呼吸も心臓も停止しているのではなく、忘れているような状態にあった。普段生活しているときのような、無意識にオートマチックな動きをしているのに似ている。
これはいい、とタンノは思う。
呼吸の苦しさから解放され、予想が当たった嬉しさと見えない命綱でつながれたような少しの安心感が心に灯った。先ほどの激しかった水流が嘘だったように、いつの間にか水中は穏やかになっていて、タンノはイルカが泳ぐような動きでスムーズに進んでいく。
しかし、どんなに泳ぎ進んでも対岸にぶつかる気配はなかった。
浮かび上がって周りを見てみると、向こう側の岸も自分がいた岸も見えなくなっていた。永遠に続く白い水面と白い天井しか見えず、太平洋の中心に浮かんでいるような気分になった。
360度途切れる事なく広がるかすかな水平線を見て、タンノは急に孤独になり、心細くなった。何かを叫んでみようとしたが、恐怖のせいなのか白い水を飲んでしまったせいなのか声が出なかった。
嫌だ、誰か、と心の中で叫び、再び水に潜って一心不乱に泳ぎ始めた。
両手をまっすぐに伸ばし、水をかき混ぜるみたいに揃えた両足を動かした。
恐怖から逃れるように猛烈な勢いで泳いでいると、両手の先が硬い壁にぶつかった。勢いが余ってタンノは頭までぶつけてしまう。しっかりとした痛みがあったが、それよりも辿り着いた嬉しさでいっぱいになった。
水中から顔を出すと、そこにあったのは先ほどまで見ていた白い世界ではなく、室内プールのような場所だった。
自分がどこから来たのか、タンノには検討もつかなかった。
小学校のプールの二倍ほどの広さで四方はプールサイドで囲まれており、無限に広がっていたはずの空間は跡形もなくなっていた。天井には体育館にあるような白い水銀灯が等間隔につけられ、周りは白い磨りガラスで囲まれている。
目を上げるとプールサイドに女が立っているのに気付いた。女は看護師が着るような白い作業着の格好をして、タンノが上がるのを待っていた。
この場所は何なのか聞こうとしたが、声は出ないままだった。
タンノがプールサイドに上がると、女は手に持っていた服を差し出した。タンノは自分が裸であることを思い出し、慌てて服を受け取る。女は薄い笑みを浮かべていたが、笑っているのではなく元々そういう顔に作られているようだった。相手を不快にさせるわけでもなく、かといって安心させるものでもない、とても中立的な微笑みだ。
体を濡らしていた白い水は空気に触れると急速に乾き、タンノはすぐに服を着た。服はやわらかい和紙でできていて、病院の検査で着るものと似ていた。
女は目でついてくるようにタンノを誘導し、プールの角にあったドアを開けた。
ドアの向こうでは待合室のような場所で、タンノと同じ服を着た人間が何人も座っていた。
(続)
![]()
![]()
![]()
![]()
 GRAPEVINE 「1977」 2013.06.22
GRAPEVINE 「1977」 2013.06.22 第六話 「水平線」 2013.07.09
第六話 「水平線」 2013.07.09 オニギリpart2 2013.06.24
オニギリpart2 2013.06.24 ふつうのモチと茹でたモチ2 2013.07.12
ふつうのモチと茹でたモチ2 2013.07.12 めんつゆトラップ 2013.07.09
めんつゆトラップ 2013.07.09