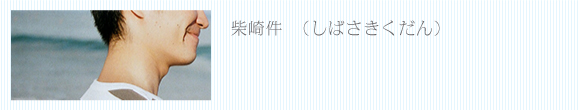![]()

2013.09.17
第二十五話 「不可逆」
タンノに関する物がすべて消え失せているということを除いて、真由美の部屋は元の現実とほとんど変わっていなかった。いつもの癖で危うくベッドに倒れ込んでしまいそうになったが、悲しい疎外感がタンノを引き止めた。
フローリングの床にあぐらをかいて部屋を眺める。
目に映るどれもが見慣れているものなのに、その全てに対してぎこちない距離をとらなければならない事が、タンノを余計に孤独にさせた。
コーヒーをスプーンでかきまぜる音が背中の方で聴こえる。
決して心地良くはない緊張感が、そこには含まれていた。
タンノは少しだけ振り向いて真由美を見る。固くなった真由美の背中が目に入ると、すぐに視線を戻した。
噓でもないし、夢でもない。
真由美にとって自分が存在しない世界が、あまりにも自然に目の前に広がっている。
片桐が煙草を吸っているときもそうだったが、この世界が本当に本物の現実のように見えてしまうことがある。
その境界は常にはっきりと切り分けられていなければならないし、この世界に浸食されてはいけない。
タンノは心の中で強く念じた。
この世界と元の現実との差異を明確に確認し続けなければ、いずれ元の現実を忘れてこの世界がほんとうになってしまう。
真由美がコーヒーを運んで来るまで、二人は一言も発さなかった。
カップをガラスのテーブルに置く時、鋭い音が鳴った。
このテーブルで何度もお茶を飲んだり食事をしたりしてきたが、タンノがそんな音を聞くのは初めてだった。
「ありがとう」
タンノは揺れて輝くコーヒーの暗闇に向けて言った。
「温かいので良かった?」
真由美が訊く。
「うん、大丈夫」
そう言って、湯気の立つ暗闇を少し啜ってみせた。コーヒーの香りと薄い苦みで、タンノの頭はほんの少しだけ落ち着いた気がした。
真由美も両手でカップを持って、舐めるように啜る。
カップをテーブルに置いて、また鋭い音が鳴る。
それが開始の合図であるみたいに、真由美は話を始めた。
「それで、今日はどうしてうちに来たの? というか、よくこの場所がわかったね、誰かから聞いた?」
「近藤」
タンノはほぼ自動的に答えた。
「近藤君?」
「そう、近藤。あいつもこの辺に住んでるだろ? それで、住所教えてもらったんだ」
タンノは作った笑いを浮かべてコーヒーを一口飲んだ。
さっきよりも苦みが増している。
近藤は高校の同級生で、二人の共通の友人だった。かわいいものや華やかなものに女子よりも敏感で、身なりに人一倍気をつかう男だった。フラワーアレンジメントの仕事をしていて、代官山にあるフラワーブティック(要するに花屋だ)で働いている。
この世界にも彼が存在していることに、タンノは少し安心した。
「そう、それで、実は俺も最近この辺りに引っ越して来たんだ。それで近藤から、佐野さんもここらへんに住んでるって聞いて、ちょっと近くまで来たからつい、尋ねちゃった」
突然でごめんね、とタンノは真由美のコーヒーカップに向かって言った。
「なんだ、そうだったんだ。急に来たから何かあるのかと思ってびっくりしちゃったよ」
真由美はそう言って溜め息を吐いてから、初めて笑ってみせた。
「手みやげの一つでも持ってくれば良かったね、ごめん」
彼女の笑顔を久しぶりに見た気がして、タンノも自然に笑った。
「だってもう、何年も会ってないでしょう? ずっと会いたいなって思ってたけど、都合が合わなくて、会えないまま連絡もとれなくなっちゃって……」
「そっか」
会いたいと思ってくれてたのか、とタンノは胸の奥に喜びを感じた。
「そっかじゃないでしょ、もう。いつの間にか携帯の番号もアドレスも変わっちゃってるし、なんで教えてくれなかったの?」
ごめん、とタンノは咄嗟に応じる。
「多分、携帯無くしちゃって、佐野さんの連絡先もわからなくなっちゃったんだと思う」
「多分て何よ」 もう、と言って真由美は口を尖らせてみせる。
「いや、よく覚えてなくて、ごめん」
「なんだかタンノ君、高校の時とあんまり変わってないわね。相変わらず、ぼんやりしてる」
真由美が呆れたように言うと、タンノは鼻を擦って誤摩化した。
嬉しい事など一つもない状況なのに、どうしてこんなにも心がくすぐったくなるのだろう。
彼女と話をしているとタンノはどうしても、高校時代の片思いしていた頃を思い出してしまうのだった。おそらくタンノに対する彼女の口調や対応が、その当時のままだからだろう。
元の現実にあった親しさは微塵も無くなっているが、その代わり、誰にも踏まれていない一面の雪みたいな関係があった。
性格も人格も変わっていないのであれば、この世界でも彼女ともう一度恋が出来るのではないだろうか。
タンノはそう思って、ほんの少しだけ心を浮かべた。
「最後に会ったのっていつだっけ? 覚えてる? 俺もう、忘れちゃって」
タンノが訊くと、真由美は眉を寄せて、うーんと小動物のような声で唸った。
「高校卒業して何回か会ったきりだから、ほんとにちょうど十年前くらいかな。でも、急に会えなくなっちゃったでしょう、私、タンノ君に避けられてると思ってた」
「どうして? なんで俺が避けるんだよ?」
タンノは真由美の言葉に不意を突かれて笑った。
「だって、私たちが付き合い始めてから、タンノ君、急にそっけなくなっちゃったじゃない」
真由美はそう言って、体育座りの格好で膝を抱えて体を揺らす。
タンノの顔が笑ったまま固まる。
「私たちって?」
タンノは静かに揺れる彼女の髪の毛を見て訊いた。
「私と、トモヤ君」
「トモヤ君?」
真由美は揺らしていた体をぴたりと止めて、笑顔の消えたタンノの目をじいっと覗く。
「覚えてなわけないでしょう? アオキ君よ、アオキトモヤ君」
アオキ君? と、タンノは頭の中で言う。
三途の白い川で、すまん、と頭を下げたアオキの後頭部を思い出した。
(続)
![]()
![]()
![]()
![]()
 GRAPEVINE 「1977」 2013.06.22
GRAPEVINE 「1977」 2013.06.22 雨2 2013.07.02
雨2 2013.07.02 茹でたモチボーリング 2013.07.09
茹でたモチボーリング 2013.07.09 太陽の泡 2013.07.03
太陽の泡 2013.07.03 「三宅洋平」について 2013.07.23
「三宅洋平」について 2013.07.23