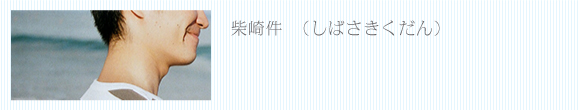![]()

2013.08.16
第十七話 「現実分岐」
店を出ると、太陽は相変わらず叩きつけるように人や建物を照らしていた。
首から流れた汗が、シャツに染み込んでいく。
二人は暑さから逃げるように、足早にコンビニエンスストアへと向かう。
普段と同じように行動していてください、と店を出る前にタンノは言った。
「俺が刺されるのは、コンビニを出てすぐなので、それまでは何も意識せず普段通りに振る舞っていてください」
「それはいいけど、なんか、武器とか用意しなくていいのか? 犯人捕まえるんだろ?」
「そうですね……、何がいいでしょうか」
「何も考えてないのかよ? これから刺されるかもしれないんだろ?」
「いや、致命傷さえ避けられればいいと考えているので……」
「何なんだよその余裕、死ななければどうなってもいいみたいな感じだな」
死ななければどうなってもいい、確かにそうだ、とタンノは思う。
死にさえしなければ、腕を切り落とされても目をつぶされてもいいのかもしれない。
俺の本当の現実は、別の世界にあるのだから。
「いえ、そういうわけではないのですが、少し考えがあって。俺が刺されるとき、つまり店を出る時ですが、記憶では片桐さんが俺の前を歩いていて、俺は片桐さんの後ろを歩いていたんです。刺された後に、片桐さんが振り向いたのを覚えています。なので、コンビニを出るときはその逆に、片桐さんは俺の後ろを歩いてください」
「それで?」
「それで、犯人らしき人間が俺に近づいてきたり接触したりしたら、思いっきりタックルしてほしいんです」
「タックル?」
「はい、タックルです」
「タンノ君、マジで言ってるの?」
片桐は口だけで笑ってみせた。
「はい、片桐さん、アメフトやってましたよね? 大学時代」
「やってたよ。中学、高校、大学、ずっと」
「社会人になってからも少しやってたんですよね」
「やってたよ、やってましたよ」
「思いっきりタックル、お願いしたいんです」
「マジで?」
片桐は今度はしっかりと笑い出した。
タンノもつられて少し笑った。
「アメフトの試合に刃物持った奴なんていなかったよ?」
「だって、言ってたじゃないですか、俺のタックルなら相撲取りでも弾き飛ばせるって」
「いや、まぁ、それは言ったかもしれないけどさ。昔の話だよ」
そう言って、片桐は煙草の先を灰皿で叩いた。
落ちる灰を見て、ずれていたはずの目の前の現実がいつの間にか自然なものとして見えている事に、タンノは気がついた。
本当の世界でも片桐が煙草を吸っていたのではないかと思ってしまいそうだった。
危険だ、とタンノは思う。
「とにかく、お願いします」
タンノはまっすぐに片桐を見る。
片桐は笑いを落ち着かせてから言う。
「でも、もし刺されちゃったらどうするのよ?」
「自分自身も気を張って注意深くしているので、気配を感じたら対処できるかと」
ふうん、と言って片桐は煙草を灰皿に押し付ける。
虫が殺されるみたいに、煙は小さく昇って消えていった。
「なんだか要領を得ないんだよなあ、漠然としてる。刺されるっていうのに危機感があまり無いみたいに見えるんだけど」
「記憶が曖昧なせいもあるかもしれません。それか、自分自身がまだ、すべてを信じきれていないのかもしれないです」
「警察に言っちゃあだめなのか?」
「多分取り合ってくれませんし、何より、普段と違う事をして犯人が俺を刺すという未来が変わってしまうのを避けたいんです」
「それはわかるけど、そうだとしたら、もうこの話を俺にしてる時点で遅いんじゃないのか?」
「そうですけど、だから、なるべく普段と同じにしたいんです。それに、この話をしないと俺はまた刺されて死ぬ事になりかねないので」
「うん、よしわかった、言う通りにしよう」
片桐は観念して言った。
「ありがとうございます」
タンノは申し訳なさそうに頭を下げた。
「タンノ君、なんだか変わったなあ」
ファミリーマートの店内にあるフリーザーの前でアイスを選んでいる時、片桐が言った。
「変わりました?」
「うん、なんか、前まではそんな事言う人じゃなかったのに」
「全部、その変な夢のせいです」
タンノはアイスが並ぶフリーザーに向けて言う。
「うん、そうなんだけど、なんか面白くなったよ」
「そうですか?」
薄く笑う片桐を見る。
古い写真を見て懐かしむような笑顔だった。
「いいと思うよ、そういうの」
片桐はガリガリ君を手に取って言う。
タンノは何も言わず、あずきバーを選んだ。
二人とも、いつも通りの味を選んだ。
会計を済ませて自動ドアが開くと、さっきまでは聞こえなかった蝉の声が、鼓膜を叩くように鳴り響いていた。
(続)
![]()
![]()
![]()
![]()
 恋するクレヨン 2013.07.15
恋するクレヨン 2013.07.15 musiquoとmusiquo musiqua 2013.08.09
musiquoとmusiquo musiqua 2013.08.09 miscorner/c+llooqtortion ミスコ-ナ-ル-クト-ション 2013.08.23
miscorner/c+llooqtortion ミスコ-ナ-ル-クト-ション 2013.08.23 だし、みこし、おおだいこ。 2013.09.12
だし、みこし、おおだいこ。 2013.09.12 「空白連鎖」書籍篇(文学フリマサンプル) 2013.10.30
「空白連鎖」書籍篇(文学フリマサンプル) 2013.10.30