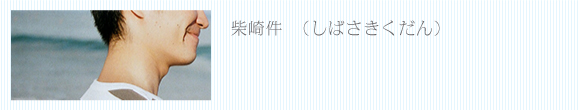![]()

2013.08.20
第十八話 「回避と逃避」
タンノは片桐に目を合わせてから会社へと歩き出す。
無言で頷いた片桐の瞳にも、緊張の光が見えた。
タンノはアイスの袋を開けようとするが、手に力が入らず指先がうまく動かない。
自分が動揺している事を認識すればするほど、心臓の鼓動は速くなり、息が浅くなっていった。
犯人の服装くらい覚えていれば、警戒すべき人間をある程度はしぼる事ができたのに。
視界に入ってくる様々な人を目でなぞりながらタンノは思う。
タンノの記憶や頭の中の映像には、犯人に関するものは少しも残っていなかった。
思い出せないのではなく、始めから存在していなかった。
当たり前だ、とタンノは思う。
痛みとショックでそれどころではなかったのだ。
しかし、せめて男か女かだけでもわかっていれば少しはマシだったのに。
タンノは愚痴を吐くように頭の中でつぶやいた。心臓の昂りのせいか、余計な言葉が次々と頭の中に流れ込んでくる。
タンノは、濡れた犬がするみたいに首を細かく振って、雑念を追い払った。
ヒントのない神経衰弱のように、すべての人間に対して意識を向けなければならなかった。
袋がようやく開けられると、中から固く凍ったあずきバーを取り出して小さく噛んだ。まるでこの世界が夢ではないことを強調するみたいに、普段よりもしっかりとした歯ごたえがあった。しかし、口の中で溶けていくアイスは冷たいだけで、味は感じられなかった。唾と一緒に飲み込んで、タンノはまた一口かじりついた。
アイスを食べているのではなく、ただ冷たい塊を喉に流し込んでいるようだった。
「タンノ君、まだかな? これから来るのかな?」
横断歩道で信号が変わるのを待っている時、後ろを歩いてきた片桐が小さな声で言う。
「わかりません、でも、この後だと思います」
タンノも声を潜ませて答えた。
わかった、と片桐は小さいため息と一緒に吐いた。
横断歩道の向こう側で信号待ちをしている人々を見ていると、タンノは白い世界で見た三途の川を思い出した。
あの時、あの白い激流を渡りきっていたら、こんな世界でこんな事をせずに済んでいたのかもしれない。
目を覚まして真由美の顔が見られたのかもしれない。
会いたいな、真由美。
タンノは白いワンピース姿の恋人を頭に浮かべて思った。
信号が青に変わり、人々が水が流れるみたいに歩き出す。
タンノもその流れに飲まれるように踏み出した。
通り過ぎる人々の顔を、視線を刻み付けるように見る。
目の前の人間を見ていても無駄だ、とタンノは自分に言う。
犯人は俺の死角から来るのだ。
タンノは視線を下に落として後方をうかがった。しかし、見えるのは誰かの足元ばかりで、いきなり襲われたとしても対処できそうにはなかった。
さきほどまでうっすらとしか感じていなかった恐怖が、急にはっきりとした輪郭をもってタンノの足元に転がり始めた。
何故だろう、とタンノは考え始める。
片桐さんの言う通り、これから刺されるというのに、何故俺はこんなにも余裕を持っていられたのだろう。
これが虚の世界だからだろうか。しかし、目の前に広がっているのはまぎれもない現実だ。
死ななければどうなったっていい?
そんなわけがあるか。
またあの痛みを感じるかもしれないのに、そしてまた死んでしまうかもしれないのに、この世界が本当の世界ではないからといって、俺は単純に考えるのを放棄していただけだったのではないか。
タンノは腹に刺さったナイフの存在を思い出す。腹に埋まった刃の感触を、記憶の中で再現した。
心臓が一つ動くごとに血が滲み、流れ出し、切り裂かれた皮膚や筋肉や細胞が悲鳴を上げるみたいに痛みを訴える。
俺はただ倒れてうずくまって、呻き声をあげるだけしかできなかった。
怖かった。
痛かった。
逃げたかった。
一秒後、五秒後、十秒後、三十秒後、一分後、刺されるかもしれない。
もう一度、あの痛みを味わうかもしれない。
それなのに何故俺は、平気でいられたのだろう。
何故わざわざこんな場所に立っているのだろう。
犯人が知りたい?
知って、それでどうなる。
俺はそれよりもまず、生きなければいけないのだ。
その未来から逃げなければ。
タンノは足元に流れていく白黒の道を睨みつける。
もう認めてしまおう、これが噓の世界だとしても、確かな現実であるということを。
そして、その現実でまた同じ痛みを味わうのは怖いのだ。
早く、この場所から離れなければ。
心に決めたタンノは恐怖で震える顎を鳴らしながら、片桐の方を振り向く。
「片桐さん」
震える眼球から涙が溢れてきそうだった。
「逃げましょう」
怖い夢を見て怯える子供のように、タンノの声は細く震えていた。
「わかった」
片桐はタンノの声を真剣に受け止める。
横断歩道から会社までの道を、二人は全速力で走り抜けた。
タンノの心は、ライオンに追われる草食動物そのものだった。
死にたくない、死にたくない、死にたくない、死にたくない。
会社に辿り着くまでのおよそ一分間、タンノの頭はそれだけを考え続けた。
自分の靴音も、周りの騒音も、街の暑さもうるさい光も、すべてがタンノから離れていくように感じた。
ほとんど自動的に足は地面を蹴り続け、身体は乗り物に乗っているように決まった速度で前に進んでいった。途中、持っていたあずきバーが手から離れていったが、タンノは気付かずに走り続けた。
会社のビルに辿り着き、自動ドアがゆっくりと開く。
競馬の埒が開くみたいに駆け込んで、タンノはロビーにあるソファに倒れ込んだ。暑さと恐怖の汗で、体中は雨に打たれたみたいに濡れていた。呼吸が細かく繰り返されて、心臓が暴れ出すみたいに血液を叩き流している。必要以上に効いた冷房が、むさぼるように体の熱を奪っていく。
仰向けになって天井を見る。手に触れるソファの布が懐かしく感じられた。
呼吸がほんの少し落ち着きはじめた頃、息の切れた片桐が入ってきた。
「タンノ君、速すぎるよ」
片桐はそう言って、タンノの正面にあるソファにどっかりと体を置く。
すみません、とタンノは息だけで応えた。
二人はしばらく、それぞれの呼吸を整えた。
片桐が「しんどい」とか、「あつい」とか、「死んじゃう」などと言うたびに、タンノはすみません、と返事をした。
「ちょっと水買ってくるわ」
片桐は大きく呼吸を吐いた後、そう言って行ってしまった。
タンノは天井をずっと見ていた。
ここの天井、こんな色をしてたのか。
電気のついていない蛍光灯を眺めたあと、目を閉じて、まぶたの裏に光る緑色を見ながら思う。
生きている、良かった。
これからどうなるんだろう、俺。
その二つのフレーズが、タンノの頭の中で交互にリピートした。
(続)
![]()
![]()
![]()
![]()
 GRAPEVINE 「1977」 2013.06.22
GRAPEVINE 「1977」 2013.06.22 電源タップさん 2013.07.10
電源タップさん 2013.07.10 氷さん 2013.08.14
氷さん 2013.08.14 Hexenhaus : Hänsel und Gretel 2013.08.21
Hexenhaus : Hänsel und Gretel 2013.08.21 文学フリマについて 2013.11.03
文学フリマについて 2013.11.03