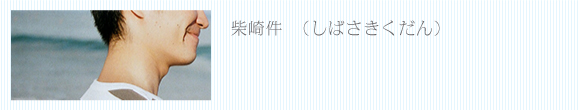![]()

2013.09.10
第二十四話 「新しい再会」
真由美はドアを開けずにタンノの返事を待つ。
すぐに顔を出してくれると考えていたタンノには予想外だった。
真由美はそんなに用心深かっただろうか。
そう思いながらタンノはドアを見つめた。ドアは空の写真が褪せたみたいな色をしていて、 タンノが好きなはずの色だったが、閉じられたままのドアは奇妙な世界につながる扉のように見えた。
「どちら様ですか?」
真由美の少し苛立った問いに、タンノは反射的に答える。
「タンノです、タンノアキラです」
喉の奥から咄嗟に出てきた声は、ひどく掠れていた。
口の中がひりひりと乾いているのに気がついた。
一瞬の沈黙が流れる。
アキラくん、と言ってガチャリとドアを開けて、笑顔の真由美が出てくる。
そんな願いを込めてタンノは想像をしてみたが、この現実は違っていた。
「ごめんなさい、どちらのタンノさんでしょうか?」
不審者に対する敵意を露にした声で真由美は訊く。
恋人の冷たくなった口調に、胸のあたりが凍り付いた気がした。
今までに聴いた事のない、なんの愛情も情けもない声に、タンノの心が悲しく震える。
外の雨は止んでいたが、風と雷鳴が戦うみたいに空で唸っている。
どちらのタンノさんでしょうかって?
どちらもこちらも、タンノさんは俺しかいないですよ。
あなたの恋人のタンノですよ。
真由美さん、忘れたんですか。
冗談は辞めてください。
お願いです。
僕です。
わかるでしょう。
そう言いながら、思いっきりドアを叩いてしまいたかった。
乾いた喉が水分を欲して、何度も唾を飲み込む。
「○○高校の、タンノです」
タンノが言うと、閉まったままのドアの向こうで真由美が動きを止めたのがわかった。
「○○高校のタンノって、三年四組の……?」
「そうです、三年四組のタンノです」
チェーンのかかったままのドアがわずかに開いた。
「タンノ君?」
開いた隙間から真由美の声がこぼれる。
タンノが隙間を覗くと、そこには元の現実と少しも変わらない真由美がいた。しかし、その目には恋人に対する柔らかさややさしさは一つも灯っておらず、疑いの光だけが広がっていた。
タンノはその視線を感じて、急に暗い宇宙に放り出された気持ちになった。
苦しくて誰もいない、孤独な世界だ。
本当に俺のことを忘れてしまっている。
忘れてしまっている、というよりも、彼女の中に、最初から無かった事になっている。
芝居じゃないのはわかっている。
それでも、冗談だと言ってほしい。
噓でもいいから、噓だと言ってほしい。
タンノはそう思いながら、小さく震える足を密かにつねった。
「こんにちは」
右手を中途半端に上げて、哀しみで出来た笑顔をはりつけた。
真由美の姿は元の世界と何一つ変わっていなかった。
こじんまりとした肩に華奢な髪の毛が垂れている。
タンノを見る眼差しだけが、決定的に違っていた。
「こんにちは、どうしたの? なんでタンノ君が、いきなり?」
真由美は何かを探すように、辺りを見回した。
真由美の困惑した表情にタンノも困惑した。
歯切れの悪い言葉だけが、古い井戸の不純物みたいに流れ出てくる。
「ごめん、急に。その、用はなかったんだけど、いや、無いわけじゃないんだけど、なんか、ちょっと会いたくて、会いたいというか、話したい事がある、っていうわけでもないけど……」
タンノは鼻の頭をかきながら言う。
何かを思い出しそうだった。
どこかで感じた事のある雰囲気と、気持ちだった。
そうだ、確か高校の頃、真由美に初めて話しかけたときもこんな感じだった気がする。
結局何が言いたいか伝わらなくて、気まずいままその日は終わってしまったのだ。
それを見ていたアオキが、いろいろ仲を取り持ってくれたんだよな。
それでちゃんと話せるようになったんだっけ。
昔なんか懐かしんでる場合じゃないのに、なんなんだこの気持ちは。
タンノは自分自身に少し呆れた。
真由美は必死に言い淀むタンノを訝しげな目で見る。
「なんだかよくわからないけど、用が無いわけないでしょう。十年ぶりに会いにきた友達が、そんなにびしょ濡れになって……」
真由美はそう行って、チェーンを外した。
「どうぞ入って、今タオル持ってくるから」
タンノは自分でも何を言っているかわからないような返事をして、玄関に上がった。
真由美に渡されたタオルで髪を拭いていると、嗅ぎ慣れた匂いが頭の奥まで広がった。
真由美の部屋の匂いだ。
タンノが何を話せばいいか考えながら時間をかけて拭いていると、真由美が訊く。
「ねえ、あなた本当にタンノ君よね?」
質問の意味がわからなかったが、タンノはタオルのお礼を言いつつ答えた。
「うん、本当にタンノだよ。急に来ちゃってごめん、佐野さん」
タンノは高校時代の呼び方を最後に添える。
俺は十年ぶりに会いにきた、高校時代の友達だ。
その言葉を呼吸と一緒に、何度も反芻した。
(続)
![]()
![]()
![]()
![]()
 GRAPEVINE 「1977」 2013.06.22
GRAPEVINE 「1977」 2013.06.22 ネコアイス 2013.08.11
ネコアイス 2013.08.11 ネコとチンアナゴ4 2013.09.11
ネコとチンアナゴ4 2013.09.11 タマシー3 2013.10.04
タマシー3 2013.10.04 エッセイについて 2013.10.08
エッセイについて 2013.10.08