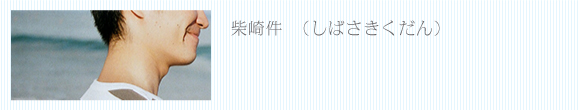![]()

2013.10.15
第二十九話 「抵触」
タンノはエンドウカオリの呼吸を胸に感じながら、目に刺さる照明を薄く開いた目で眺めていた。カオリの心地良い重さと熱を感じているうちに、状況を無視したささやかな微睡みがやってくる。
瞼を閉じて、重なる心臓の音を聴いた。自分の重く騒がしい鼓動とは逆に、彼女の心臓は寝室のドアをノックするようにやさしく響いていた。
タンノはカオリに気付かれないように鼻でゆっくりと息を吸って、彼女の匂いを肺の中に取り込んだ。匂いが肺から体内に染み込んでいくのを感じると、禁じられた薬物みたいに脳の中で何かが弾ける感じがした。花びらがそのまま気体になったみたいな匂いだった。
微睡みが少しずつタンノの思考を奪い、状況から逃げるように意識が落ちかけたとき、カオリは乱暴に身体を引きはがして立ち上がる。
「帰る」
タンノに対する全ての興味を失ってしまったみたいに、カオリはそれだけを冷たく吐いた。
身体に触れていた熱が一瞬で霧散してしまったような気がして、タンノは反射的に呼び止める。
「ちょっと待って」
カオリはタンノの言葉を無視してローファーをこつこつと鳴らし、ドアノブに手をかける。
「上がっていかない?」
女子高生を相手に俺は何を言っているんだろう、とタンノは思う。
「なんで? 家に入っちゃいけない約束でしょ? タンノ君がだめって言ったんじゃない」
カオリは投げ捨てるように言ってドアを開ける。
約束?
俺はそんな約束なんか知らない。
おまえは何を知ってるんだよ。
教えてくれよ。
俺は何も知らないんだよ。
そう思いながら、タンノはカオリの背中に向けて言う。
「話がしたいんだ」
タンノが言い終わる頃にはカオリは玄関を飛び出して、ドアは叩き付けられるように閉められた。
タンノはその場に座り込んだまま、カオリのぬくもりを剥がすみたいに胸や腹をがりがりと爪で擦った。散乱した靴を眺めながら、固まったように視線が動かなくなってしまった。
エンドウカオリの髪の毛や輪郭や感触が頭の中で自動的に再現されるのを、タンノはずっと眺めていた。眺めているうちに、さっきまで溢れていた体の中の感情が消滅していくのがわかった。
タンノは重い動作で立ち上がり、部屋に戻ってベッドに腰をかけた。体がいつもより重く沈み込むような気がした。背中を丸めたまま携帯電話を手に取って、カオリへのメールを打つ。
全てを正直に、話せることは話そうと思った。
『エンドウカオリさん、突然で驚くかもしれないけど、最後まで聞いてください。僕は今日、とある事情で記憶を失ってしまいました。正確に言うと、あなたのいない世界を今まで生きて来て、急にあなたのいるこの世界に連れて来られた、ということなのだけど、記憶をなくしたと言った方がわかりやすいので、そのように捉えてください。
僕自身、事情や状況がわからない部分もあるのですが、今の僕は、エンドウさんの知っている僕ではありません。全くの別人だと思います。その証拠に、僕はエンドウさんのことを一切知らないし、思い出す記憶も持ち合わせていません。謝るのが正しいのかわかりませんが、こんな事になってしまい、ごめんなさい。
こんな事に巻き込んでしまいながらこんな事を言うのも厚かましいのだけど、もしよければ、今まであなたが見て来た僕について、教えてくれませんか。僕がどのように生きていて、どうやってあなたと出会い、あなたとはどういう関係だったのか。』
メールの返事は一分もしないうちに返ってきて、それから何通かやりとりがあった。
『いつまでふざけてるの?』
『ふざけてなんかいません、でも、あなたの知っているタンノはもう死んでるんだと思う。』
『バカにしてるの? それともバカになったの?』
『バカにしてはいないけど、バカになったと思ってもらった方が都合が良いかもしれない。』
『じゃあもう終わりなの?』
『終わりと言われても、君との間で何が始まっていたかも知らないんだよ。バカにしてるんじゃなく、本当に教えてほしいんだ。』
そのメールのおよそ十分後に、エンドウカオリから電話がかかってくる。
「もしもし」
タンノが話しかけるが、カオリは何も言わず、鼻をすする音だけが聞こえてくる。泣いているのだ、とタンノは思う。外にいるのだろう、無言の奥で道路の音が聞こえる。車が通り過ぎる度に、雨が降っているような音が響く。
「もしもし」
タンノは沈黙の中にもう一度呼びかけた。
雨に似た車の音に耳を傾けながら、タンノは空白の中に一つの答を見つけ出していた。
(続)
![]()
![]()
![]()