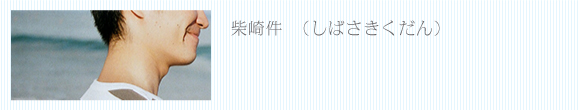![]()

2013.10.01
第二十七話 「遭遇」
タンノは手の中で光る「エンドウカオリ」の文字を見つめた。
伝わってくる着信の振動が、不吉な生き物のいびきみたいに響いてくる。
この生き物を起こしてはいけない、と思いながら頭の中で話しかけた。
誰だ?
エンドウカオリ、何の用だ?
俺はあんたなんか知らないぞ。
あんたは俺の事を知ってるのか?
電話に出たら教えてくれるのか?
俺はもう、恐いのだ。
あまりにも自然に変わってしまったこの世界が。
とにかく俺は帰りたい。
そうだ、帰ろう。
とりあえず家に帰ってみよう。
帰ってシャワーを浴びて、横になろう。
そういえば今日は日曜日だった。
もっとゆったり過ごしてるはずなのだ。
日曜日はいつも……。
日曜日はいつも真由美と夕飯を食べていた、その事を思い出すと、また内臓が消えたみたいに体の中が寂しくなった。
携帯電話はいつの間にか震えるのを止めていて、指先に振動の残骸だけが残っていた。
ズボンのポケットに隠すように携帯電話を戻して、タンノは静かに歩き出した。
自分の存在が薄くなって軽くなってしまったような気分だった。
帰り際、ポストに書かれた「佐野」の文字を一瞥する。
何を思えばいいのだろう?
悲しい? 辛い? 寂しい? 悔しい? 苦しい?
種類としてはそれらに似ているが、感情の正確な正体がわからなかった。
恋人でなくなってしまった真由美を目の当たりにして、それは辛かった。辛くて寂しいことだった。
しかし、変わってしまった真由美はあまりにも自然で現実的で、今までの自分が間違っているようにさえ思えた。
リアルな夢ではなく、リアルな現実を見ているのだ、とタンノは思った。
この世界では自分の方が間違っている、そう思うほか無い。
もしかしたらこの現実になじんでいく事が、この世界でスムーズに生きていく方法なのかもしれない。元の現実とこの現実との差異を明確にしなければならないと思っていたが、それを感じながら生きていくにはあまりにも厳しすぎる。
元の世界は元の世界として、今のこの世界はこの世界として、全く別のものと考えるべきなのだ。ほとんどのものが元の世界と変わらないから、少し解釈を間違えていたのかもしれない。きっとそうだ。
タンノは強引に心を落ち着かせた。
しかし、今の状況を慰めるには、十分な考えだった。
タンノはアオキについて思い出した。
アオキが生きていることについても、どう思えば良いかわからなかった。
死んだ友人が生きていて、それが自分の恋人と付き合ってるという状況に遭った人間は、自分の他にいないだろう。
ただ少しだけ、心が懐かしくなったのは確かだった。彼が生きていて今何をしているのか、どのような人生を送りどのような人間になっているのか気になった。
タンノはふと思いついて、携帯電話で実家に電話をかける。
呼び出しから間もなく、母親の声が聞こえた。
「なに? どうしたの?」
母親がこの世界でも変わらず存在していることに、タンノはとりあえず安心した。
「ごめん。ちょっと、送ってもらいたいものがあって。高校の卒業アルバムなんだけど、屋根裏部屋にしまってあるやつ。あれちょっと送ってくれないかな?」
「卒業アルバムなんて何に使うのよ。屋根裏のどこにあるの?」
「手前の方にある段ボールに入ってると思う、多分」
「ふうん、わかりました。急ぎなの?」
「別に急ぎではないけど、ちょっと必要で」
「あんた、そんなに遠いわけじゃないんだから取りに来たらいいじゃないのよ。ごはんも食べていけばいいし、たまには顔見せなさい」
「はい、うん、わかった。わかったわかった」
いつもなら鬱陶しいだけの母親の小言も、タンノには嬉しく感じられた。
電話を切った後、実家の方は何も変わっていないのだろうと思って、小さく頷いた。
アオキが死んでいないのなら、卒業アルバムにも彼が生きてる人間として写っているはずだ。あの事故がほんとうに真由美の言う通りで、アオキがほんとうに死んでいないのかを確かめたかった。
真由美の家を出てから数分ほどで、タンノは自分の住んでいる小さなマンションに到着した。
表札にある自分の名字を確認してから鍵を開ける。
佐野真由美の部屋に入った時とは逆に、何も変わっていない懐かしい匂いがタンノを迎えた。
ただいま、と普段なら言う事のない台詞を玄関に置いて、一直線にベッドに向かい倒れ込んだ。
シャワーを浴びなきゃ、と瞼の暗闇を眺めながら言う。
仰向けになって深い呼吸を慎重に何度も繰り返した。
飼い犬を撫でるみたいに、指先でベッドの感触を確かめる。
俺の家だ。
帰ってきたのだ。
そう思って、ほんの少しだけ涙がにじんだ。
この世界から逃げ出そうとするみたいに、眠りは急速に広がっていった。
目が覚めた時には元の世界に戻っていますように、と決して叶う事はないであろう願いをタンノは思い続けた。
太ももで、着信の振動が鳴っている。
何度か無視していると、観念したように携帯電話は息をひそめた。
浅い眠りの中で、タンノはいくつもの夢を見た。次々と流れていく風景を見て、夢の中でも疲れていくのがわかった。あるとき、夢の中で夢だと気付き、タンノは自ら意識を現実に戻す。
不完全な眠りでどれだけ寝ていたかわからなかったが、窓の外はすでに夜に切り替えられていた。
まだ微睡みの中にある意識の中に、インターホンの音が降り落ちてきた。
凍った水をかけられたみたいに、タンノの体は緊張で固くなる。
重力になじんでしまった体をゆっくりと起こし、重い足取りで玄関へと向かう。
言葉にならない縒れた声とともにタンノがドアを開けると、そこには高校の制服を着た髪の短い少女が立っていた。涙が瞳の中で揺れて、照明の光が散らばっている。
タンノが何かを言おうとした瞬間、少女の両腕がタンノの首を掴んだ。
少女はタンノの眼をしっかりと睨みつけたまま、細く固い指で握りつぶすみたいに首を絞める。
タンノは止められた呼吸の中で、少女の宇宙のような瞳に見とれていた。
(続)
![]()
![]()
![]()
![]()
 ネコアイス 2013.08.11
ネコアイス 2013.08.11 レイニーレイニー 2013.06.22
レイニーレイニー 2013.06.22 音楽の海岸 2013.07.04
音楽の海岸 2013.07.04 茹でたモチ畑 2013.07.08
茹でたモチ畑 2013.07.08 いくえみ綾 「私がいてもいなくても」(2) 2013.07.04
いくえみ綾 「私がいてもいなくても」(2) 2013.07.04