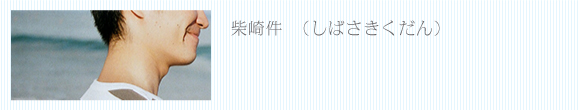![]()

2013.09.24
第二十六話 「改竄」
エアコンの風が、汗と雨で濡れていた服をすっかりと乾かして、さらに熱を奪っていく。タンノは体が少しずつ凍えていくような気がした。さっきまで湯気を立たせていたコーヒーも熱を失って、体温と同じくらいになったカップを指先でなぞる。
こんな真夏の真っ昼間に、どうして熱湯で淹れたコーヒーなんかを飲まなければならないのだろう。タンノはわざと頭の中で愚痴をこぼした。
しかし、真由美がアイスコーヒーの作り方を知らない事を、タンノは知っていた。どんな季節でもどんな天気でも、出てくるのはいつもホットコーヒーだった。目の前にいる人物が紛れもなく本物の佐野真由美であることを突きつけられている気持ちになった。
「聞いてる?」
真由美の声でシャボン玉が弾けるみたいに、タンノは我に返る。
「ああ、聞いてる、聞いてるよ。付き合ってたんだね」
タンノは、プラスチックで作ったような安っぽい笑みを口のあたりにはりつけた。
「付き合ってたんだねって、知らないわけないでしょう。なんだか、しばらく会わないうちに何もかも忘れちゃったみたいね」
真由美はこじんまりした鼻で、小さいため息を吐く。
「今も、付き合ってるの?」
タンノはコーヒーカップにかちかちと爪をぶつける。
「うん、今も付き合ってるよ。こんなに長く付き合うなんて思ってもなかったけど」
真由美は少し照れくさそうに言った。
どこかで聞いた言葉だ、とタンノは思う。
ああそうだ、俺がアオキに言った言葉じゃないか。
ちくしょう、とわずかに声に出してしまったが、真由美には届かなかった。
ちくしょう、ともう一度胸の中でつぶやく。
胸には氷で出来た棘がいくつも刺さってるみたいに寂しかった。
アオキが死んだはずのあの時のことはどうなっているのだろう、とタンノは思う。
「そうだ。高校のとき、三年の夏にバーベキューやったよね?」
タンノは思い出を見つけたように訊く。
真由美はコーヒーを口に含んだまま何度も頷いてから、ごくりと飲みこんで答えた。
「うん、やった。あの時、ほんとに大変だったね、二人とも生きててほんとうに良かったわ。今思い出しても背中がぞっとするもん」
「どんな感じだった?」
「どんな感じって、何が?」
「その、俺とアオキが川に入って、どうなったっけ?」
タンノは誘導尋問をするみたいに言葉をつなげた。
真由美は少し思い出してから言う。
「タンノ君が滝壺みたいな、川の深くて流れの速いところにはまって戻ってこれなくなっちゃって、それを助けにトモヤ君が泳いで行ったんだけど、二人とも全然帰ってこなくて、もうほんとに、こっちが死んじゃいそうなくらいハラハラしたよ。もうほんとに帰ってこないんじゃないかと思った」
「でも、ちゃんと帰ってこれたんだよね」
「そうよ、もうタンノ君、水いっぱい飲んでぐったりしてて、トモヤ君が必死で引っ張ってきたの。覚えてないんだっけ? 救急車呼んだり人工呼吸したり、引っぱたいたり大声で呼びかけたり、みんなほんとにやばいって思ってて、でも途中で気がついて意識が戻ったから、ほんとに安心したのよ。タンノ君の目が覚めたとき、腰抜けちゃったもん、私」
「大変だったんだな」
「タンノ君、意識無かったから覚えてないのかもしれないけど、ほんとに大変だったのよ」
「俺はアオキに命を救われたってことか」
「そうよ、命の恩人なんだから、もっと大切にしてあげてよね。トモヤ君も、タンノ君に会えなくなってから相当落ち込んでたんだから」
「そうなのか」
そういうことになっているのか、とタンノは思う。
真由美が携帯電話を手にとって言う。
「ねえ、今からトモヤ君呼んでもいい? 今日、日曜だから家にいると思うし、タンノ君が来てるって言ったらきっと喜んで来ると思うの」
真由美の指がリダイヤルのボタンを押す。
「いや、今日は遠慮しておくよ」
タンノが慌てて出した手がコーヒーカップにぶつかる。
半分ほど残ったコーヒーが日本海の波のように揺れて、少しこぼれてしまった。
ごめん、とタンノは言う。
「何で? トモヤ君と会うの嫌? 会いたくないの?」
真由美は携帯電話を耳から離し、テーブルに置いた。がちん、という音がする。
「嫌ってわけじゃないけど、久しぶりだし、突然だし、もっと落ち着いた時に会いたいと思って……」
不自然に慌てるタンノを見て、真由美は疑うように、ふうんと言った。
これ以上ここにいるのは危険だ、とタンノは思った。
他人のものになってしまった恋人の話を聴くのも辛かったし、アオキが生きている世界も恐かった。真由美がアオキの事を「トモヤ君」と呼ぶ度に、錆びたナイフで肌を削られるような気持ちになった。
「今日は急にお邪魔して、ごめんね」
ごちそうさま、と言って立ち上がった時、膝がテーブルにぶつかってまたコーヒーが少しこぼれた。
真由美はそれを見て吹き出して笑った。
「何やってんの、タンノ君」
口に手をあてて笑う真由美を見て、寂しさと愛しさが破裂するみたいに溢れてきた。やわらかく垂れる髪や白く薄い肌に触れたくなったが、目を逸らしてやり過ごし、代わりに哀しい笑顔を持ち上げた。
別れ際、タンノは住所と電話番号を紙に書いて渡した。住所を見て真由美は、ほんとうに近いんだね、と驚てみせた。
当たり前だ、とタンノは思う。
俺が君の家の近くに引っ越して来たのだから、近所であるのは当然なのだ。
またね、と言ってドアが閉まり、内側からチェーンがかけられる音が聞こえると、真由美とのつながりが切断されたみたいに思えた。しかしそれは、元々つながりの無い関係を目の当たりにしただけのことだった。
真由美はこの世界に存在した。
内面も外見も、何も変わっていなかった。
ただ関係だけが変わってしまっていた。
タンノは胸の中の氷を溶かすみたいに、胸に手を強く押しあてた。
心臓の音が鳴って、呼吸のたびに肺が膨らんで縮んだ。
ドアの方を振り返る。
その奥に真由美はいる、しかし、それはもう違う真由美だ。
タンノは瞬きを一つして別れを告げた。
夕立はすっかり止んで、外には雲と青空が散らばっていた。
ため息を吐いてズボンのポケットに手を突っ込んだとき、間違えてスイッチを押してしまったみたいに携帯電話が震え出した。
見てみると、タンノの目に先ほど電車の中で見た名前が映った。
エンドウカオリからの着信だった。
(続)
![]()
![]()
![]()
![]()
 aus 「Closed」「Opened」 2013.07.18
aus 「Closed」「Opened」 2013.07.18 GRAPEVINE 「1977」 2013.06.22
GRAPEVINE 「1977」 2013.06.22 鉄の結晶 2013.08.11
鉄の結晶 2013.08.11 ひかりとかげ 2013.10.12
ひかりとかげ 2013.10.12 第二十八話 「位相」 2013.10.08
第二十八話 「位相」 2013.10.08