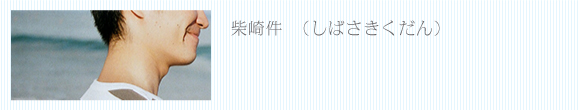![]()

2013.11.12
第三十話 「融解」
汗をかいたアイスコーヒーのグラスを傾けて舐めるように啜ったあと、にがい、と言ってエンドウカオリは舌を出した。
「ガムシロップ、もうちょっと入れようか?」
タンノは自分のグラスを傾けながらカオリに言う。ぶつかる氷の音が、よそよそしく鳴る。
いらない、と言ってカオリは首を振り、もう一口啜ってみせた。
木製の低いテーブルを挟んで、エンドウカオリとタンノは座っていた。
無言の電話が切れたあとすぐにインターホンが鳴り、何も言わずにカオリは部屋に入って来た。瞼は少し腫れていて、何度も鼻を啜った。
汗ばんだカオリの首筋を眺めながら、タンノは彼女の言葉を待った。自分から何かを口にするべきかもしれないと思ったが、彼女の中にある疑問に答えるのが先だと考えた。
アイスコーヒーの氷が溶けるかすかな音が響いてくるほど、部屋の中は静まり返っていた。
グラスに触れるカオリの指を眺めていると、タンノは小さく輝く指輪に気が付いた。首を絞められているときはわからなかったが、淡い黄金の、線の細いシンプルなデザインの指輪が右手の薬指にはめられていた。
どこかで見覚えのあるものだった。
「その指輪……」
タンノが不意に口をすべらせる。
「なに?」
グラスを眺めていたカオリが、視線だけでタンノを見る。
「いや、その指輪、良いね、綺麗だ」
タンノの言葉に肩を落として、カオリは溜め息を吐いた。出来の悪い子供にするような、突き放すような溜め息だった。
「演技ではないのね?」
はめられた指輪を逆の指で弄りながら、カオリが言う。
「演技?」
棘に刺さらないように、タンノはなるべくやわらかく声を発する。
「タンノ君が買ってくれたのよ」
カオリは溢れ出そうになる涙を押し込めるように、無理矢理に唾を飲み込んだ。
カオリの言葉に、タンノは何も返せずにいた。タンノがその指輪に見覚えがあるのは当たり前だった。それは元の世界の恋人である佐野真由美に買った物とほとんど同じ品だったからだ。佐野真由美にプレゼントしたものはピンクゴールドだったが、エンドウカオリの指にあるのは品のある黄金だった。色が少し違うだけで、同じ商品だろうとタンノは思った。
タンノは自分の指先に視線を落とし、また何を言うべきか考えた。
カオリは指輪を外して、音を立てずにテーブルの上に置く。
木目の上に黄金が鈍く光る。
「なんで記憶が無くなっちゃったの?」
カオリは指輪に向かって言う。
「なんでかと言うと……」
タンノがどう話そうか迷っていると、カオリは追い立てるように言葉を重ねた。
「いつから記憶が無いの? わたしのことはもう、全然覚えてないの? なんでわたしのことは忘れてるのに自分のことは覚えてるの? 自分の名前とか、家とか、仕事とか、会社とか、そんなことは忘れてないんでしょう? なんでわたしのことだけ忘れてるの?」
震える唇を見て、タンノの胸に悲しい棘が刺さる。
理解されることはないと思いながら、ありのままを話そうとタンノは口を開いた。
「僕は、今まで君のいない世界を生きてきたんだ。僕が元々いた世界に君はいなかった。それがとある事情で、今日の午後から、僕はこの世界で生きることになった。だから君の事は忘れるというよりも、最初から何も無いんだ」
タンノはカオリの目をまっすぐに見つめて、テーブルに身を乗り出して言う。カオリはタンノの瞳の奥に噓を探すように、深く突き刺すみたいな視線を返す。涙で薄く濡れたカオリの瞳を見ていると、タンノは思考はすぐに吸い込まれてしまいそうになる。
「じゃあ今までわたしと一緒にいたタンノ君はどこに行っちゃったの?」
「それは……」
それは、どこに行ってしまったのだろう。
どこか別の場所で生きているということはきっと無いだろう。
俺がこの世界に来る事によって、この世界で生きていた彼の二十数年の人生が消えてしまったのだろうか。
そんなことは考えもしなかった。
しかし、この世界は疑似空間で、俺が生き返る為に用意された世界のはずだ。
だから、今まで生きて来た別の俺がいたとしても、今の俺がその彼に対してできることなどは何一つない。
「わかった」
タンノが考えを巡らしているうちに、カオリは答を見つけたみたいにして言う。
「あなたが殺したのね?」
カオリの瞳から絞ったように涙が落下した。
(続)
![]()
![]()
![]()
![]()
 ハナエ 「変幻ジーザス」 2013.09.13
ハナエ 「変幻ジーザス」 2013.09.13 GRAPEVINE 「1977」 2013.06.22
GRAPEVINE 「1977」 2013.06.22 aus 「Closed」「Opened」 2013.07.18
aus 「Closed」「Opened」 2013.07.18 鉄の結晶 2013.08.11
鉄の結晶 2013.08.11 第二十八話 「位相」 2013.10.08
第二十八話 「位相」 2013.10.08