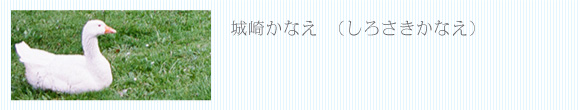![]()

2013.10.31
猫について(文学フリマサンプル)
11月4日の文学フリマで販売する書籍の一部です。
猫についてと、本についてのエッセイを書きました。
よく触るようになった近所の猫と、読もうと思っても読めない本についてです。
ここでは猫についての一部を掲載しています。
—————————————-
猫について
最近、猫によく触るようになった。触るようになったというか、触らせてくれるようになった。猫は近所に住んでいる野良猫で、近所のいろんな人から餌やご飯をもらっている。昼は散歩に忙しく、夜は駐車場の車の下で夢を見ていた。
三ヶ月間に私が引っ越してきてから、猫はすぐに目に付いた。猫はいつもふたりで行動していた。ひとりは耳の欠けた三毛猫で、もうひとりはグレーに黒の縞が入った猫だった。近所に住むスナックのママが、三毛猫の方をミケ、黒い縞の猫をノラと呼んでいるので、それに倣って呼ぶことにしよう。
最初は、遠巻きに眺めているだけだった。はじめから触れるとは思っていなかったので、触ろうともしなかった。こちらが好意を抱いているからといって、そんなに都合良く向こうから寄ってきてくれるほど甘くはない。というよりも、近寄って逃げられるのが悲しいから、自分から距離をとったのだ。なんだか、自分の異性に対する接し方に似ている。自分なんてどうせ相手にされないだろう、と思って何もしないくせに、気づいてもらいたくて視線を振りまいたりする。猫にまでそうするなんて、少し切なくなってしまう。話を戻そう。私はふたりに出会う度に挨拶をしたり、目がゆっくりと閉じていくのを眺めていたり、毛繕いするセクシーポーズに喜んでいた。
ある深夜に、黒い縞の猫、ノラだけが歩いていた。私も夜の散歩をしているところで他に誰もいなかったので、しゃがんで話しかけた。(周りに誰かいたら、恥ずかしくて話しかけられない)
「こんにちは、今日はひとりか」
私がしゃがむと、ノラは小さい声で「なーん」と鳴き、私の足にすり寄ってきた。いいの? 触っていいの? と心の中で尋ねながら、少しべとついた柔らかい毛に触った。触っても大丈夫なことを確認すると、両手で揉みこむようにこねくり回した。偶然出くわした韓流スター(氷川きよしでも可)に触れるオバサンのように、あるいはライブ会場で近くに来たジャニーズに触れる中学生のように、頭や腹や腰や喉などあらゆるところを、ここぞとばかりに撫で回した。なるべくノラが気持ちよさそうな部分を撫でてやると、仰向けになって腹を広げてみせた。服従のポーズだ。私は調子に乗ってくりくりくりくりといつまでも撫で続け、ノラはいつまでも撫でられ続けた。このまま撫で続けていたら朝になってしまう、と思うほど撫でたあと、私は気持ちを振り切るようにしゃきっと立ち上がり、ノラに別れを告げた。ノラは「なーお、なーお」と小さく鳴いていた。触ってくれてありがとう、か、おまえ触りすぎだよ、か、もっと触ってくれよ、か、触らせてやったんだからなんかくれよ、のどれかだと思った。
その日から、わたしはノラを見る度に触りまくることになった。買い物に行くときや、散歩に行くとき、昼夜かまわずそれは行われた。しかし、もう一方の猫であるミケには近付くことが出来なかった。ふたりが寝ているところに私が行くと、ノラは近付いてきたがミケはさっさとどこかへ行ってしまった。少し手を伸ばそうとしただけで、警戒して逃げてしまうほどだ。ミケとノラのふたりの関係がどんなものであるかわからなかったが、私はふたりに触りたい、と思った。なんとなく、ノラだけをこねくり回しているのが、ミケにとって申し訳ない気がした。
ある時、彼らの名付け親(?)であるスナックのママがふたりにごはんをあげているところに出くわした。ミケもノラも、お皿に乗せられたペディグリーチャムみたいなおいしそうなお肉をかつかつと食べている。そこでママと話して、彼らの名前を知ることになった。「ノラは触れるんですけど、ミケが触らせてくれないんです」と私が言うと「餌をあげるといい、餌がなきゃ寄ってこないよ」と教えてもらった。その時、ママの持っていた餌を手に乗せてもらいミケにあげた。ミケは警戒しながらも、はぐはぐと食べて手のひらを舐めた。
「たまに餌を買ってやりなさい」とママに言われたが、未だに餌をあげられていない。彼らと出くわすタイミングと私が餌を持っているタイミングが合わなかったりするのだ。
それからまたしばらくした後、夜にノラと遭遇した(黒い体をしているので夜だと気づきにくいのだ)。私は散歩を始めたばかりだったので、少しノラの体をこねてからすぐに立って、ノラと一緒に歩くことにした。ノラは横について歩いてきてくれたので、なんだか感動した。見えない糸でつながっているみたいだった。小学生の頃も、男の子と少し仲良くなっただけでもうその人と結ばれたような気持ちになったが、それと似たような感覚だった。何年ぶりだろう。いや、その話はやめよう。
児童館の広場のような小さい公園に通りかかったとき、ノラはてってってっとベンチの方に歩いていった。私も付いていってベンチに座った。ノラが足元で「なーおなーお」と鳴くので、私は「おいで!」と言って膝をぽぽんと叩いた。すると、しゅるしゅるっと見えない階段を上るように、ノラは私の膝の上に乗ってきた。至福のときが訪れたのだ。膝に乗るあたたかく丸々とした体を、ときに揉み込むように、ときに手のひらで毛並みを楽しむように、余すことなく撫で回した。季節は秋の真ん中だったが、そこまで寒くもなく風もほとんど吹いていなかったので、空気も気持ちよく、いつまでもここにいたいと思った。ノラはすっかりくつろいでいるようで、十分経っても二十分経っても三十分経っても離れようとしなかった。
——————————————–
このあと、悲しい結末が。
書籍に続きます。
![]()
![]()
![]()