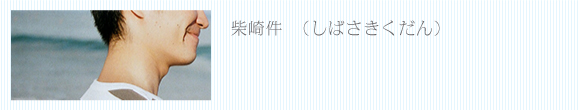![]()

2013.12.03
第三十三話 「融解4」
「一緒に寝る」
タンノは確認するように、口の中だけで言う。
それは彼女に向けての質問でも疑問でも、肯定でも否定でもなかった。
カオリはタンノの言葉を無視し、土を掘る犬みたいにもぞもぞと掛け布団の中に入って、身体をなじませるように体勢を整える。タンノに背を向ける格好で横になると、枕にやわらかい髪の毛がさらさらと垂れるのが見えた。
タンノは指先一つ動かす事ができないまま、重力に従う彼女の後ろ髪を眺めていた。
幾重にも交差して散らばる髪の毛の一本一本を視線でなぞり、そのカーブや光の反射から触り心地を想像した。
撫でたらきっと、指の間を滑るように通り抜けていくだろう。
瞬きをせずに見つめながら、タンノは思う。
カオリはタンノに背を向けたまま何度か呼吸をした後、少しも動かなくなってしまった。呼吸や心臓の鼓動さえも感じられないほど、正確に静止していた。
時間の無い宇宙に放り出されたみたいに、二人はどちらとも動かなくなった。タンノは微かに動くだけで、その宇宙のバランスが崩れて元に戻れないような気がしていた。
タンノにはカオリが目を開けているのか閉じているのかさえもわからない。
タンノは視線だけを動かして、彼女の後頭部と、テーブルのコップと、自分の指先を交互に見ていた。時間を過ごす事で目の前の状況が解決することは決してないが、自分がどのような行動をとっても間違いになるような気がした。彼女に何か声をかけることも、言葉の通りに一緒に寝る事も、ここから逃げ出すことも、どの選択肢もしてはいけない事だと思った。
もしかしたら彼女に対する自分の行動に正解などないのかもしれない、とふと思い、きっとそうなのだろう、と納得した。
それからタンノはどこでもない空中を眺めた。
ほんの少し考えるのをやめて時間を過ごそうとおもったが、蛍光灯の音や冷蔵庫の唸りや彼女の気配や匂いが蓋の無い器官から入り込んでくるのがわかった。
どうすればいいだろう、彼女を無理矢理にでも帰せばいいのだろうか。
それとも彼女の言葉の通り、一緒に寝ればいいのだろうか。
彼女は、最後に、と言った。
最後に、一緒に寝ない? と。
もし一緒に寝てしまったら、もう現れないのだろうか。
もしそうならば、それはしてはいけない気がする。
きっとこの世界では、俺にとって彼女の存在が必要なのだ。
この世界での俺を支えてくれていた唯一の人物なのだ。
いなくなられたら、多分、俺は一人になってしまう。
元の世界とこの世界との明らかな差異である彼女の存在が、俺の存在を明確にしてくれる。
この世界の住人ではないということを証明し続けなければ、俺はきっとこの世界になじんでしまう。そして、この世界で生きる事が本当の人生になってしまうだろう。
だから、それを防ぐ為にも、彼女が必要なのだ。
でも、だからと言って、今の俺に何ができるのだろう。
何をするのが正しいのだろう。
空中に散らばる蛍光灯の光を眺めながらタンノは考えたが、答えはどこにも見つからなかった。
いつの間にか丸くなっていた背中を正そうとしたとき、ねじを巻かれたみたいに急にカオリが顔をこちらに向けた。
タンノは小さく驚いて、カオリに目を合わせる。
カオリは太陽が沈むみたいな遅さで、ゆっくりと瞬きをした。
長い瞬きの間、タンノの周りから音が消えていた。
瞬きを終えて眠りから覚めたように目を開くと、彼女は少し笑いながら枕に頭を軽く擦り付けて言う。
「タンノ君の匂いだ」
花の匂いを嗅ぐみたいに、カオリはタンノの匂いを鼻の奥や肺の中に取り込んだ。
薄い笑顔を保ったまま、カオリは震える声で言った。
「わたし、タンノ君のこと、ほんとうに好きだったんだよ」
喉が震えて、笑った瞳から大粒の雫がこぼれ落ちる。
タンノは彼女の濡れた視線と目を合わせながら息を飲んだ。
カオリは隠れるように布団をかぶり、身体を震わせた。
タンノの探していた答が、彼女の涙によって導かれた気がした。
タンノは考えるのをやめて、彼女の隣に潜り込み、微かな力で抱きしめた。
腕に、彼女の骨がやわらかくぶつかる。
鼻先にある髪の毛からカオリの匂いが頭の奥に広がると、これで良かったのだ、とタンノは思った。
いつまでも続く涙とささやかな嗚咽を胸に感じながら、壊れてしまわないように、タンノは彼女をただ柔らかく抱きしめていた。
(続)
![]()
![]()
![]()
![]()
 GRAPEVINE 「1977」 2013.06.22
GRAPEVINE 「1977」 2013.06.22 めんつゆトラップ 2013.07.09
めんつゆトラップ 2013.07.09 落ちる雲 2013.08.21
落ちる雲 2013.08.21 手のひらからさらさら 2013.08.22
手のひらからさらさら 2013.08.22 フーリン 2013.08.25
フーリン 2013.08.25