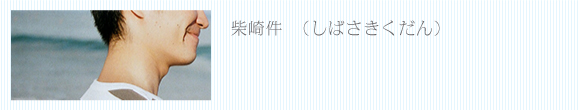![]()

2013.07.02
第四話 「癖」
あごの肉をつまむアオキを見て、タンノはボロボロになった漫画を思い出した。
ある朝、教室の最前列に座ってるアオキが、朝礼の間、遠くを見ながら延々とあごの肉をつねっているのにタンノは気がついた。視点は黒板の方を向いているのに、現実とは違う景色を見ているようだった。休み時間にタンノが何かあったのかと話しかけてみても、アオキは視線を落としたまま、何でもない、と答えた。
アオキはその日、一日中うわのそらで、いつもなら猿のように舞うはずの体育のバスケットボールの授業でも、しぼんだ風船みたい周りに合わせてのろのろと揺れているだけだった。その時も、感触を確かめるように自分のあごをずっと触っていた。一度もボールに触れようとしないアオキを見て、タンノは心配になった。
放課後、タンノがもう一度問いかけようとしたとき、アオキは教室に響き渡るでかい声で、すまん! と叫び、タンノに頭を下げた。その巨大な声といびつな光景に、教室に残っていた大勢のクラスメイトが静まり返った。
頭を下げたままいつまでも顔を上げないアオキとクラスメイトの視線によって、タンノはわけもわからないまま顔を赤くした。
タンノは半ば無理矢理アオキを教室から連れ出し、校舎を出た。
一体何があったんだよ、とタンノが訊くと、アオキはもう一度、すまん、と言って、鞄の中からボロボロに破れた漫画を取り出した。
その漫画はタンノがアオキに長い間貸していたもので、タンノ自身も貸していたことを忘れていたものだった。
ウチのコタローが喰いちぎってしまって……、と言って、アオキはまた深々と頭を下げた。
コタローというのはアオキの家で飼っている柴犬のことで、アオキに似てちょっと気性の荒い、乱暴者だった。
タンノは前屈しているみたいに深く下げられたアオキの後頭部を見ているうちに拍子が抜けて、呆れと安堵とともに妙な笑いがこみ上げてきて吹き出してしまった。アオキは突然の笑い声に驚き、顔を上げて目を丸くした。
そういう男なのだ、とタンノは思った。普段は周りの事など何一つ気にする事なく、あれほどがさつで大雑把に振る舞っているのに、ひょんなところで神経質で気が小さいところがあった。
タンノが、その漫画は古本屋で百円で買ったものだからまったく大丈夫だ、と伝えると、アオキは、先に言えよバカヤロウ、と涙目になりながら力なく怒ってみせた。
アオキは何か言いたくない事や言いづらい事や隠し事があるとき、決まってあごの肉をつまむ癖があった。
「アオキ、なんで真由美がこっちに来るんだ?」
タンノが訊いてもアオキは答えなかった。
Tシャツから伸びるアオキの腕に、見覚えのない傷跡がいくつか見えた。溺れたときのものだろうか、とタンノは思い、少し胸が痛んだ。
「タンノおまえ、刺されたときのこと、本当に覚えてないんだな?」
アオキはあごをつまんだままタンノに訊く。
タンノは軽く首を振った。
「覚えてない。どうしてか、そこだけ記憶が隠されたみたいになってるんだ。夢を見てたのに内容は覚えてないのと似てる。刺された事は覚えてるのに、それ以外の事はさっぱりだ。多分、ショックでそうなったんだと思うけど」
「ずいぶん冷静なんだな」
「冷静というか、あんまり何かを感じたり考えたりっていうのができないんだよ。夢のなかっていうのはそういうもんだろ?」
「いや、おまえは普段からどんなときも冷静だったよ。ほら、俺が川でいなくなったときだって、平気な顔してたじゃねえか」
アオキは視線を落として、二人を隔てる白い川を見ながら言う。
「何を言ってるんだ?」
タンノは眉をしかめた。
アオキは自分を戒めるように小さく頷いた後つまんでいたあごから手を離し、心に決めたようにタンノを見つめた。二人の間には相当な距離があるはずなのに、その視線はとても力強く、タンノは耐えられずに視線をそらした。
「佐野はおまえを呼びにくるよ。こっち側に来るように、呼びに来る」
アオキはそう言った後に、すまん、と言って頭を深く下げた。
ボロボロになった漫画の時と同じ後頭部が見えた。
「なんで……」
なんでおまえが謝るんだ? と言いかけた時、瞬きをした隙にアオキの姿は消え、代わりに白いワンピースを着た佐野真由美が立っていた。
鈍い光をまとったような真由美の姿は、世界の白に溶けてしまいそうだった。
![]()
![]()
![]()
![]()
 GRAPEVINE 「1977」 2013.06.22
GRAPEVINE 「1977」 2013.06.22 いくえみ綾 「私がいてもいなくても」(3) 2013.07.11
いくえみ綾 「私がいてもいなくても」(3) 2013.07.11 aus 「Closed」「Opened」 2013.07.18
aus 「Closed」「Opened」 2013.07.18 鉄の結晶 2013.08.11
鉄の結晶 2013.08.11 ネコアイス 2013.08.11
ネコアイス 2013.08.11