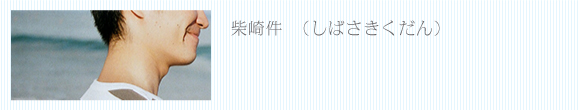![]()

2013.09.03
第二十二話 「接続」
タンノの会社から真由美のアパートの最寄り駅まで行くには、多少時間がかかる。
地下鉄で八駅ほど乗り、そこから私鉄に乗り換えてさらに八駅ほど行き、駅を出てからさらに二十分ほど歩かなければならなかった。
疲れきった会社帰りに真由美のアパートに行く時にはその距離を憎んだが、今のタンノにとっては少しありがたかった。
タンノは地下鉄に揺られながら、体が倒れてしまわないようにつり革を両手でしっかりとつかむ。日曜の昼間だったが、車内には客が多く乗っていた。夏休みだからだろうか、比較的若い人間が多く見える。
タンノは周りを見回した後、暗闇の窓に反射する自分と目を合わせた。
瞳はうつろで少し涙が溜まっているように見え、髪は四方に散らばっていて、シャツは汗と走った動きによってしわくちゃになっていた。タンノの重くくたびれた雰囲気が、これから行楽に行くような浮かれた客との対比によって浮き彫りになる。
掴んだつり革に体重をかけて、タンノは静かに溜め息を吐き、目を閉じる。
何も考えたくはなかったが、何かについて頭を働かせていないと、体中の力が抜けてしまいそうだった。
何について考えよう。
そうだ、乗り換えの時にペットボトルの飲み物を買おう。
今年の夏は異常に暑いし、油断しているといつ脱水症状とか熱中症になるかわからないからな。
毎年、今年の夏は暑いと言ってる気がするけど。
汗はいつの間にか出てくるし、体力も気付かないうちに消耗してくる。
何がいいだろう、スポーツドリンクかお茶か水か。
甘いものがいい、なんとなく。
塩がいいらしけど、しょっぱい飲み物なんて置いてないからな。
頭の中で独り言を続けているうちに、タンノの耳にノイズが染み込んでくる。電車が揺れて軋む音と、エアコンの風の音だ。エアコンの風向きがタンノの方を向く度に、シャツと髪の毛が乱暴に吹かれていた。乗車した時には体中にまとわりついていた熱と汗が、どこかに消えてしまっているのに気がついた。
ドアの上につけられた電光掲示板を見る。「Next stop is」の文字が右から左に流れた後、乗り換えの駅が表示された。
いつの間に八駅も過ぎたのだろう、とタンノは思う。頭が相当ぼんやりしているからなのか、この世界が変わってしまったからなのか、違和感の原因がどこにあるのかわからなくなっていた。
車内アナウンスの後、電車はすぐに駅に到着した。がりがりと音をたててドアが開き、他の降りる客の流れに乗ってタンノも電車を降りる。
タンノは半ば無意識に、視界に入った自動販売機に向かって一直線に歩いた。陳列されたディスプレイのペットボトルの中から、目に留まった「梅塩みかん」という商品をタンノは選んだ。
「塩」という文字が入っていたのでつい買ってしまったが、これはうまいのだろうか。
よく冷えたペットボトルを手に取って、タンノは思う。
乗り換えのホームまで歩きながらペットボトルに口をつける。喉を通った後に、意外と悪くない、と誰に言うでもなくつぶやいた。グレープフルーツに塩をまぶしたような味だと思った。
私鉄への連絡改札を抜けて、電車を待つ。
タンノは向かいの壁に気に入っている女優の広告を見つけて、ぼんやりと眺めながら電車を待った。美しく加工された髪の毛や鼻すじや肌を見て、ほんの少しだけ幸せな気分になる。しかし、間もなく轟音とともにやってきた電車にその広告は潰されてしまう。こんなものに見とれてないで自分の状況をちゃんと見ろ、そう言われたような気がした。
ドアが開き、タンノは鉄よりも重い足取りで歩を進めて乗り込んだ。車内は地下鉄よりも空いていたので、タンノは空いている座席の端に座った。
電車が発車して、やがて地上に出る。窓の外に、威圧するように立ち尽くすビルとその奥にぽっかりと浮かぶのっぺりとした入道雲が見えた。
邪魔だな、とビルに向かってタンノは思う。
入ってくる太陽の光が、窓のシルエットを床に正確に落とす。
タンノはゆっくりと形を変える影を見ながら、ポケットから携帯電話を取り出した。
エンドウカオリ。
俺はこの人物とどういう関係なのだろう。
身に覚えの無いメールや着信の履歴を見てタンノは思う。
「遠藤香織」と表示された名前を頭の中でもう一度復唱した。履歴から見てみると、タンノはこの遠藤香織という人物と、週に一、二回会っているようだった。待ち合わせのメールの前後に、着信や発信が残っている。
俺はこの人と付き合っていたりするのだろうか。
この人と話すとき、一体なんて言えばいいのだろう。
タンノはいつのまにか硬く瞑っていた瞼の中で、あの医者を睨んだ。
相沢? 沢田?
もう名前さえもよく覚えていない。
沢なんとか、という医者。
医者の格好をした男。
あの人が悪いわけではないのかもしれないが、今は彼に憤るほかない。
もっとちゃんと説明してくれても良かったのではないか。
今考えるとあの説明は、あまりにも漠然としすぎている。
こんなことになるなら先に言っておいてくれれば、心の準備くらいはできていたのに。
生き直す、という言葉が最初からおかしかったのだ。
そもそもどうして、俺が……。
そう思ったあと、タンノは自分に言い聞かせる。
いや、違う。
根本的な原因は俺が刺されたことだ。
この現実での状況に目がくらんで、元の世界の事を忘れかけてしまっていないか?
この世界は虚なんだ。
だから別に、真由美がいなくてもほんとうは問題ないはずなんだ。
でも、この現実感の中でそれに耐えるのは難しい。
それはあまりにも、苦しい。
だから、どうか一目でも会いたい。
言葉の通り、噓でもいいから会いたい。
そうだ、もしアパートからも消えていたら、高校の卒業アルバムで確認しよう。
それで消えていたら、ほんとうに消えているのだ。
硬く閉ざしていた目をゆっくり開ける。
涙腺をしぼったみたいに、瞳には涙が薄く被っていた。床に落ちていた影は消えていて、窓の外には茶色く汚れたような雲が広がっている。夏特有の、銃弾のような雨粒を孕んだ積乱雲だ。
これから、降るのだろうか。
夏の夕立は好きだけど、嫌いだ。
電車が目的の駅に到着し、タンノは駅の外に出る。
まだ夕方にもなっていないのに、凝固した雲が太陽を隠して辺りは薄暗くなっていた。
遠くに雷鳴が聴こえる。駅前のコンビニエンスストアで傘を買おうか迷ったが、タンノはそのままアパートへと歩き出した。急げば十分くらいで着くはずだ。
大きくなる雷の音に急かされるように、タンノの足取りは速くなっていく。飛び込み台の上で背中を蹴られている気持ちになった。
あと少しでアパートに辿り着くという時に、ついに雨が降り出した。タンノは雨粒を感じて急いで駆けていったが、ほんの数十秒降られただけで、体のほとんどが雨に濡れてしまった。
上がったままの息で、タンノは集合ポストを確認する。
真由美が存在していないのならば、表札には別の人間の名前が書かれているか、何も書かれていないはずだ。
真由美の部屋である201号室のポストにゆっくりと視線を運んでいく。
そして、タンノの視線が釘付けになった。
そこには元の世界にあった表札と同じ文字で「佐野」と書かれていた。
真由美がいる。
上空で雷が威嚇するように鳴り響く。
汗と雨粒で膨らんだ雫が、タンノの首筋を滑り落ちていった。
(続)
![]()
![]()
![]()
![]()
 GRAPEVINE 「1977」 2013.06.22
GRAPEVINE 「1977」 2013.06.22 aus 「Closed」「Opened」 2013.07.18
aus 「Closed」「Opened」 2013.07.18 鉄の結晶 2013.08.11
鉄の結晶 2013.08.11 ネコアイス 2013.08.11
ネコアイス 2013.08.11 sweet : star : confliction 2013.09.04
sweet : star : confliction 2013.09.04