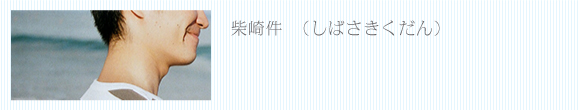![]()

2013.11.26
第三十二話 「融解3」
カオリの放った言葉が周りの空気を奪っていくみたいに、タンノの呼吸はほんの少し停止した。
喉の奥が干上がるように乾いてしまい、タンノはなけなしの空気とともに唾を飲み込む。
「そうなのか」
否定をするか、さらに質問を重ねるか、短い時間の中で迷った末、一度受け入れる事にした。
彼女の言葉だけが、この世界での自分を示している。
タンノはそう思って、咀嚼するように頷いてみせた。
カオリは記憶の中の物語を読み上げるみたいに、坦々と話し始めた。
「半年くらい前に、わたしとタンノ君は出会った。あなたはとても酔っ払っていて、道ばたで眠っていたの。わたしはそれを家に帰る途中に見つけて、声をかけた。まだ冬だったから、放っておいたら死んじゃうと思って。そうしたら、タンノ君はわたしの肩を掴んで急に泣き出して、わたしはやばいなと思ったけど、放っておけなかったから、どうしたんですかって聞いたら、好きだった人が忘れられないとか、親友に奪われたとか、絶対に俺の方が好きだったとか、こんなの間違ってるとか、そんな風に、何年も前のことをいつまでも女々しくこぼしてた。本当に、こんな情けない年上の人を見たのは初めてだと思った」
身に覚えのない濡れ衣を着せられた気がして反論したかったが、タンノは口をつぐんでその続きを待った。それに、元の世界では酔っ払って道で寝るなどありえないことだったが、この世界の自分なら、もしかしたらしてしまうかもしれないと思えた。
タンノは少しずつ、この現実での自分を理解し始めていた。
「それで、その場で愚痴を聞いていたけどいつまでも話が終わらなくて、わたしも寒くて帰りたかったから、タンノ君の家まで送る事にしたの。家に向かう間も、あなたはわたしの手を握って、いつまでも彼女のことについて話していた。最低な気分だった、声なんかかけるんじゃないと思った、すっごくお酒臭かったし、でも、見殺しにして死なれるよりはいいかと思って、それでタンノ君の家まで行ったの」
カオリはそこで言葉を区切った。
支えていた子供の自転車から手を離すように、あとは自分で漕ぎなさいというように。
「そこで、僕は君を襲ったのか」
罪を認めるようにタンノは言う。
もちろん、そんなことはしていないし、するはずもない。しかし、この世界での彼を理解すればするほど、痛いほどその心の動きを感じることができた。自棄になって酒に溺れたり誰かを襲ったりすることなど、この世界では容易にできてしまえるように思えた。
カオリからの返答が無いまま短い沈黙が生まれて、タンノは彼女に目を向ける。
カオリは諦めたように目を細くして、タンノを見ていた。視線を逸らす事なく、カオリは小さく首を横に振った。
「襲ってなんかいない。襲ったなんて、噓。タンノ君は一人で部屋に入っていったし、わたしは部屋には入らなかった。帰るときに、後で礼をさせてくれって言われて、連絡先を交換しただけ。それで、終わり」
カオリは息を一つ吐いて、肩を落とす。
「何も覚えてないなんて言うから、どうしようもない噓を吐いて、責めてやろうと思っただけ」
カオリがそう言うと、つられるようにタンノも肩を落とし、何も言わずに視線を下げた。
テーブルの上にオブジェのように置かれたアイスコーヒーの氷はほとんど形をなくして、グラスの中に透明な液体の層を作っていた。底に水滴が溜まって、小さな水たまりができている。
コースターを買おうとしていつも忘れてしまうのを思い出した。
「とにかく、それが、僕と君との出会いだったんだね。それから……」
タンノの言葉を遮って、カオリが喋りだす。
「それから何回か会ってデートするようになって、わたしはタンノ君を好きになってタンノ君もわたしのことを好きって言ってくれて、付き合おうってわたしが言ったけど彼女のことが忘れられないって言われて、じゃあ忘れるまで待つって言って待ってたのに、あなたはわたしのことなんか全部忘れてしまったの。ねえ、ひどい話だと思わない?」
ほんとうにひどい、と言って、子供が愚図るように、カオリは声を震わせる。
ほんとうに、ひどい話だ。
タンノは心の中で同意した。
「わたしはもう、必要ないのかな」
独り言のように言うカオリに、わからない、と心の中で言いながらタンノは首を振った。
カオリは小さな動作でゆっくりと立ち上がって、ベッドに腰掛ける。
「最後に、一緒に寝ない?」
タンノの目の前に投げ出された正しく折り目のついたスカートから伸びる二本の脚が、見た事のない生き物のように思えた。
(続)
![]()
![]()
![]()
![]()
 aus 「Closed」「Opened」 2013.07.18
aus 「Closed」「Opened」 2013.07.18 ハナエ 「変幻ジーザス」 2013.09.13
ハナエ 「変幻ジーザス」 2013.09.13 GRAPEVINE 「1977」 2013.06.22
GRAPEVINE 「1977」 2013.06.22 鉄の結晶 2013.08.11
鉄の結晶 2013.08.11 ひかりとかげ 2013.10.12
ひかりとかげ 2013.10.12