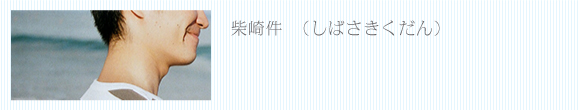![]()

2013.06.28
第三話 「対岸」
向こう岸に立つ男は、アオキというタンノの高校時代の友人だった。
アオキとは約三年間同じクラスで、同じバドミントン部だった。
アオキは顔立ちも整っていて身なりも男子高校生にしては清潔な方で、そして成績も常に上位だった。学校やクラスに数人は必ず存在する「モテるやつ」だ、と第一印象でタンノは思った。
その印象通り、アオキは多くの女子から人気があった。しかし、実際に話してみると言葉の使い方が乱暴だったり、性格も大雑把で荒っぽい一面があった。そのせいで女子たちの間では、夢中になる「かっこよくてワイルドなアオキ君」派と、離れていく「カッコいいけど乱暴者でがさつなアオキ君」派に二分した。それでも、タンノに比べればその人気は申し分ないものだった。
ある時、タンノがアオキにその振る舞いについて助言すると、アオキ自身も行動や口調や少し気にすることはあったが、しばらくして「今さらどうにもならねえ」と言って肩をすくめて見せた。諦めたようにちょっと情けない顔をしたアオキを見て、タンノは笑った。
アオキは高校三年の夏にいなくなった。
部活の仲間で集まってバーベキューをした時、タンノとアオキは酒に酔ったまま川に入って、そのままアオキだけが戻ってこなかった。風も穏やかで川の流れはとてもゆるやかっだった。タンノが上がったあともなかなか上がってこないので、はじめはどこか別の場所で上がって隠れているのだろうと思っていた。しかし、日が暮れても戻ってくることはなく、結局、どこからも発見されることはなかった。アオキは永遠の行方不明者となった。
その後、部は無期限の活動停止になり、タンノを含む部員はそれぞれに異なる期間の停学処分になった。タンノには一ヶ月の停学が下された。
もう十年も前の話になる。
白い川の向こうにいるアオキはTシャツとハーフパンツという、その当時の格好をしていた。記憶や感情が呼び出されてもいいはずなのに、タンノの心は錆びついたモーターみたいに動くことはなく、何も感じることはなかった。目の前に死んだ友人が立っている、ただその事実があるだけだった。
「本当に死んじゃってたんだな」
タンノが言う。向こう岸までは距離があったが、周りの音がないために大声を出さなくても声は届いた。
「どっかでひっそりと暮らしてるとでも思ったか?」
線の細い整った顔に似合わない太くてとげのあるアオキの声を聞いて、タンノは自分も高校生に戻ったような気がした。少しだけ、記憶のにおいが感じられた。
「みんなそう思ってたよ、ずっと。きっと、今でもそう思ってる。おまえは知らないだろうけど、何人かの女子はチームを組んで毎週土日に探してたぞ」
タンノは当時を少し思い出して話をしたが、それについてはアオキは何も言わなかった。アオキは、話すべきことはそれではない、と声に出さずに言った。
タンノは一度咳を払ってからアオキに言う。
「なんでそこにいるのがアオキなんだ? 普通、親族とかが出てくるんじゃないのか。死んだじいちゃんとかばあさんとか」
「そんな決まりなんてねえよ、なんだ、俺じゃ文句あるのか? 失礼なヤツだな……」
アオキは少し笑って舌打ちをしてみせた。
しばらく下を向いて何かを考えたあと、切り出すようにアオキはタンノに訊いた。
「佐野とはうまくやってるんだろ?」
「うん、やってる。まさか、こんなに長く付き合うなんて思ってもなかった」
佐野真由美という女は二人と同じ高校の友人で、現在のタンノの恋人である。タンノと佐野は高校二年の頃に付き合い始めて、それ以来、十年近く付き合っている。アオキはタンノと佐野をくっつけるために(タンノの恋を成就させるために)多大な世話を焼き、甚大な努力をした。アオキがいなければ、タンノは佐野真由美に挨拶すらできないまま、その恋を終えていただろう。
「真由美も俺も、今でもアオキに感謝してるよ」
そう言ってから、ありがとう、とタンノは心の中で添えた。
アオキは聞きたくもない言葉を追い払うみたいにがりがりと頭を掻いてから、あごの肉をつねる。
「佐野も、あいつももうすぐこっちに来る」
アオキは十八歳の眼でタンノを捉えたまま、優れたナイフで皮膚を切り裂くみたいに言葉を突き刺した。
(続)
![]()
![]()
![]()
![]()
 ハテンコーさん 2013.11.10
ハテンコーさん 2013.11.10 落書きの落書き 2013.06.22
落書きの落書き 2013.06.22 いくえみ綾 「私がいてもいなくても」(1) 2013.06.27
いくえみ綾 「私がいてもいなくても」(1) 2013.06.27 カボチャと月のお吸いもの 2013.07.08
カボチャと月のお吸いもの 2013.07.08 ジャスミン茶漬け 2013.07.16
ジャスミン茶漬け 2013.07.16