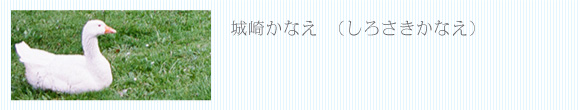![]()

2013.11.27
書く場所を求めて(前篇)
わたしはついにその場所を見つけた。
誰にも邪魔されることもなく、でも、誰もいないわけでもない。
わたしを取り囲むのは完全な孤独ではなく、他者との距離のある温かい孤独だ。
空調は常に完備されていて空間も広く、静かで、そこにいる誰もがひっそりと過ごしている。
そこではひっそりとしていなければいけないし、また、ひっそりとすることを誰もが望んでいる。
わたしはここで、時間や外につながる一切を忘れて文章を考えることができる。
わたしはその場所を、ついに見つけたのだ。
などと書いてみたけれど、いったい何のことやらわからないだろう。
なぜこんな書き出し方にしたかというと、こういう書き出し方にしたかったからだ。
それ以外に理由はない。
というわけで、はじめから、話そう。
本文が予想を越えて、あまりにも長くなってしまったので、前篇と後篇に分かれている。
ぜひ、お付き合いいただきたい。
今まで、文章を書くときは自宅での作業が多かった。
ほんのたまに、コーヒー屋や外出先などで書くこともあったが、ほとんどが自宅の、自分の机に向かって書いていた。
ところが最近、書けなくなってしまった。
環境も何も、特に変化があったわけではないのだけど、書こうと思っても、一滴の墨が水に溶けるみたいに、その気持ちはすぐに散っていってしまった。
以前は書けたのに、何故、書けなくなってしまったのか。
それは、きっと、気合いが足りないからだ。
それでは何故、気合いが足りなくなってしまったのか。
それは単純に、気持ちとか、気分とか、状況とか、そういった漠然とした問題のせいだろう。
書こう、とか、書かなきゃ、とか、書きたい、とか思っても、すぐにその気持ちは拡散してしまう。
流れていく時間だったり、暮れてしまう外の光だったり、そばにある楽器だったり、積まれたままの本だったり、いろいろなもののせいで、わたしの書こうとする気持ちはすぐに滲んでしまった。
滲んでしまうので、完全に消えるわけではなく、淡い色を残したまま、心はどんどん濁っていった。
それで、どんどん濁っていく心をどうにかしたくて、どうにかするにはやはり書く以外にないのだけど、どうしても書くことはできなくて、そうやって悶々としていくうちにストレスが溜まって、身近な人に迷惑をかけてしまったりして、これはもう、どうにかしないと、と思い、旅に出たのだ。
何者にも、自分にさえもちょっかいを出されることなく集中できるような、そんな理想の場所を探す旅に。
今までも、近所のコーヒー屋なんかを探してそこで書いてみたりもしたけれど、やはり、時間が無制限であるわけでもないし、騒がしかったりするし、まずいコーヒーを飲まなければいけなかったりする。(まずいコーヒー屋のコーヒーは、ほんとうにまずい)
一時間や二時間くらいはなんとかなるけど、それ以上は胃がもたれてくる。
そこで提案されたのが、自習室とか学習室とか呼ばれるレンタルスペースだ。
様々な人と共有していたり、完全な個室だったりする。
月々いくらとかで、朝から晩まで使えるらしい。
紹介された自習室は六本木にあって、写真で見た感じだと清潔で広々としていて、とても居心地が良さそうな場所だった。(居心地がいいからといって文章がかけるわけではないが)
月々の料金も払えなくはない程度で、設備や立地に対してはかなりの安価だった。
しかし、少しひっかかったのが交通費だった。
自宅からそこまで通うのには、往復で1000円を少し越えてしまう。
5回で5000円、10回で10000円がかかると思うと、利用する度に心が重くなっていく気がした。
そこで、近くの沿線で他に良い場所がないか、探してみることにした。
まず、自分の住んでる地域から調べてみる。
すると、近くの公民館に貸しスペースがあるのを見つけた。
一番小さい和室だと、午前と午後がそれぞれ200円、全日だと500円で借りられる。
歩いていけるので交通費はかからないから、さきほどの六本木と比べると非常に安い。
しかも八畳の個室だ、これは集中できること間違いないだろう。
予約ページを見てみる、しかし、午前か午後のどちらかは、すでに予約がとられている状態だった。
それはそうだ、こんな格安で立派な畳の部屋なのだから、利用する人も多いのだろう。
ちょうど、この日の午後が空いていたので試しにとってみようと思い、さっそくそこに書いてあった電話番号に電話をかけた。
考える前にまず行動だ、と思って電話をしたのだが、コールの際に予約はネットでするものだと気づいた。
まあいい、電話で予約をしてしまえ、と勇んで相手が出るのを待った。
呼び出し音が切れたあとに出た相手はとても感情のないしゃべり方で、これがお役所仕事か、と思う。
わたしは怯まずにありのままを伝えた。
「今日の予約をしたいのだが」
「当日の予約はできません」
「えっ……じゃあ明日の予約をしたいのだが」
「はいいつでしょう」
「午後だ」
「午後は空いてます、ネットで予約をしてください」
「了解した」
「本日中に料金をお支払いください」
「えっ……何故だ」
「ご利用日の前日までに料金をいただくことになってますので」
「そうか、了解した」
「もう会員のご登録はされてますか」
「まだだ、これからだ」
「登録しないと予約できませんので」
「そんなことはわかってる、心配するな」
「ちなみに施設のご利用は団体様のみになります」
「えっ」
わたしは無意識に通話をオフにしていた。
終わった。
こんなしゃべり方ではなかったけど、内容はこんな感じだ。
確かに個人で予約されたら公民館というコミュニティの機能がなくなってしまう。
そんなわけで諦めてさらに探すことにした。
まだ全然大丈夫だ。
気持ちは春のつくしんぼだ。
インターネットをうろうろしていると、お隣の府中市の図書館に、とてつもなく良い場所を見つけた。
なんと、学習室が無料なのだ。
それも、写真を見る限り窓もあって景色もよく、気持ちよさそうな場所だった。
隣の市でも利用できるのかチェックしたところ、利用できるらしい。
なんというか、同盟みたいな市がいくつかあって、わたしのいる市はそこに含まれていたのだ。
行くしかない。
さっそくパソコンやらポメラやらノートやら本やらを持って、完全装備で家を出た。
外は不安定な天気で、空には重い雲が光と陰のグラデーションを描いていたが、そんな描写は今はどうでもいい。
求めていた理想の場所が、もうすぐそこにあるのだ。
電車に乗っていくつか駅をやりすごして降りる。
駅を降りてから数分足らずで目的の場所に着いた。
ルミエール府中という建物の中にある、市営の図書館だ。
さすが府中市、競馬で潤っているのが手に取るようにわかる。
そんな素晴らしい建物が目の前にそびえ立っていた。
やはり無料の学習室を設けるというのは、それだけ余裕があることなのだろう。
今、わたしのその恩恵を受けるのだ。
府中市民じゃないけど。
受付のある階まで上がり、立ち尽くす係の人に想いをぶちまける。
「図書カードを作りたいのだが」
「貴様、どこの市だ?」
「多摩市だ」
「オーケー、ついてきな」
そんな感じで申込書を書くところまで案内される。
小学生のテストよりも簡単な空欄を次々と埋めていく。
名前、住所、年齢、生年月日、電話番号、メールアドレス。
そして保険証を見せて、ついにカードが発行された。
「これが図書カードだ、ここに名前を書け」
「理解した」
カキコキ
「オーケー、これが貴様の図書カードだ」
「わかってる」
「ご利用の説明をさせてもらうぜ」
「こいよ」
「貸し出し冊数は5冊以内だ、そして貸し出し期間は2週間、いいな」
「いいぜ」
「府中市にはいくつも図書館があって、どこに返してもいい」
「すげえ」
「CDとかDVDの視聴覚資料は三点以内、一週間だ、いいな」
「いいぜ」
「あとは貴様は市外だから本の予約とかリクエストとかはできねえ、わかったな、誰も市外の奴の言うことなんか聞かねえ」
「リクエストなんかしねえ」
「そして五階の学習室はご利用になれません」
「ファーーーーーーーーーーーッ!!!」
もう足も疲れたし心も疲れたよ。
ここでいっぱい集中しようと思ってたのに。
重いカバン持って、頑張ってきたのに。
なんでいつもこうなの。
わたしは渡された図書カードを持っていそいそと受付から姿を消した。
あれ、おまえ本見ていかないのかよ、なんのためにカード作ったんだよ、という係りの人の視線をふくらはぎに感じながら見えないところまで歩いた。
コートを脱いで、かぶっていた帽子をとる。
重いカバンを置いて、ゆっくりと呼吸をする。
手の中に、意味のない図書カードだけが冷たく光っている。
ぼんやりと眺めているうちに、わたしは気づく。
どこにも市外って書いてないから、これ、いけるんじゃないかな。
ほとんど無意識のまま、エレベーターの上ボタンを押していた。
五階に上がると、まぶしい光が射し込む。
学習室だ。
低いパーテーションに仕切られた机に向かっていそいそと頑張る人、窓際の席で外を眺めながらぼんやりとする人、ガラス張りの向こうの彼らは、紛れもなくVIPだった。
係りの人が見える、あの人にカードを渡すのだろうか。
そばにあった椅子に座って様子をうかがう。
後からエレベーターで上がって来た人が、なにやら機械にカードをかざしている。
なるほど、受付は自動で、バーコードを読ませるのか。
それなら係りの人を欺くよりは気持ちが軽い。
できたてのカードを機械にかざす。
まばゆい赤の光がバーコードを照らしていく……。
「ピーーーーーーーーーーーーーーーーゴリヨウニナレマセン」
「ファーーーーーーーーーーーッ!!!」
気が付いたときにはもう、わたしはモノレールに揺られていた。
体はすでに、次の場所を目指していたのだ。
(後篇に続く)
![]()
![]()
![]()
![]()
 いくえみ綾 「私がいてもいなくても」(2) 2013.07.04
いくえみ綾 「私がいてもいなくても」(2) 2013.07.04 画鋲さん 2013.07.31
画鋲さん 2013.07.31 多面体さん 2013.11.19
多面体さん 2013.11.19 2つの釈迦 2013.11.26
2つの釈迦 2013.11.26 いくえみ綾 「私がいてもいなくても」(3) 2013.07.11
いくえみ綾 「私がいてもいなくても」(3) 2013.07.11