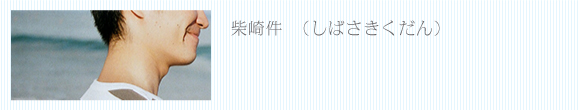![]()

2013.08.02
第十三話 「二つのドア」
相沢は部屋の奥にあるカーテンを開けて歩き出し、タンノもそれに続いて歩いた。
カーテンの奥には長い通路があった。他の建物につながる渡り廊下のような雰囲気で、両側には空気のように透き通ったガラスの窓が続いている。
窓の外には白い世界が続いていた。
相沢のサンダルの音と、タンノの素足の音が交互に響く。
遠くの正面には黒と赤の二つのドアが並んでいた。
どちらかが生き返るためのドアで、どちらかが死ぬためのドアなのだろう。
「もし、魂の死を選んだら、どうなるんですか?」
タンノは相沢の背中に訊く。
「無です。良くある答えで申し訳ありませんが、どうにもなりません、無くなるだけです。よく、眠っている状態と同じように言われておりますが、そのような感じです。しかし、決して夢も見ないし目覚める事もない。私の持論ですが、死というのはそもそも存在しないのではないかと思います。あるのは生だけで、死はどこにもない」
「死がなかったら、どうなるんでしょうか?」
「どうにもなりません、そこで終わりです。もし死を感覚的に捉えたいのであれば、想像しないことが最も近道でしょう。死を意識していない状態が、最も死に近い状態だと私は思います。単純に、他の生物はわかりませんが、人間には死を知覚する器官が備わっていないのでしょう。だから、考えたところで無駄です。問題の書かれていないテストに解答するようなものです」
相沢は背中で答えた。
一歩ずつ進むにつれて、ドアが大きく近づいてくる。
相沢は黒い方のドアの前で立ち止まり、タンノの方を振り返った。
「こちらのドアになります。このドアが、テストするための虚の空間とつながっています。夢から覚めたような感覚で目覚めると思いますが、ここでの記憶はすべて覚えているでしょう。ですが、ほとんど現実と変わらない世界なので、刺されてから今までの出来事がすべて夢であったかのような気分になるかもしれません。その方が、テストをするにも都合が良いのです。確認のためにもう一度お伝えいたします。生き返るための条件は、命をまっとうすること。事件や事故に遭わず、殺されたり死んだりしないこと、です。よろしいですね?」
相沢は鈍く輝くゴールドのドアノブに手をかけたまま言う。
「多分、大丈夫です。」
タンノは深く考えずにうなずいて見せた。
「どのような結果であれ、また私とお会いすることになると思います」
それでは、お気をつけて、そう言って相沢はドアノブを回し、ゆっくりと黒いドアを開いた。
ドアの向こうには完全な暗闇が待っていた。夜の海に、さらに墨を混ぜたような、深く底の無い闇だった。
「ここに入ればいいんですか?」
少し怖くなって、相沢に尋ねる。
「そうです。すぐに目が覚めますから、心配しなくても大丈夫ですよ」
相沢は、母親が子供を諭すような声で答えた。
タンノはつばをひとつ飲んでからゆっくりと足を踏み入れる。
その瞬間、暗闇に足を引っ張られるように、タンノの身体は落下していった。
その部屋には床がなかったのだ。
タンノは必死でもがいたが、地球の重力を何倍にも増幅させたような力で引っ張られていった。
生温かい風が、下降する身体を撫でていく。
ジェットコースターが永遠に急降下していくように、タンノの落下は長い間続いた。
いつしか、身体にぶつかる生温かい風が心地よく感じられるようになった頃、電話の呼び出し音がかすかに聴こえてきた。
知っている音だ、とタンノは気付く。
これは、会社の電話の音だ。
呼び出し音はタンノの落下につれて膨らみ、やがて耳のそばで鳴っているかと思うほど巨大になった。
もうすぐ目覚めるのだ、とタンノが思ったとき、落下した体が暗闇の床に叩き付けられた。
その衝撃で、タンノは目を覚ます。
そこは、タンノが勤めている会社のオフィスだった。
自分のデスクで居眠りをしていたらしいが、立ち上がって見回しても誰の姿も見えない。
激しい鼓動と大量の汗をかいていて、悪い夢を見た後のような気分だった。
乾いた喉が何度も唾を飲み込む。
もしかしたら、すべて夢だったのかもしれない。
あまりの現実感に、タンノは本当にそう思えた。
デスクで鳴る電話のコールは数回響いたあと、息の根が止まったように静かに鳴り止んだ。
(続)
![]()
![]()
![]()
![]()
 マグカップさん 2013.07.03
マグカップさん 2013.07.03 GRAPEVINE 「1977」 2013.06.22
GRAPEVINE 「1977」 2013.06.22 「三宅洋平」について 2013.07.23
「三宅洋平」について 2013.07.23 宮本一粋(二千花) 2013.11.08
宮本一粋(二千花) 2013.11.08 第三十二話 「融解3」 2013.11.26
第三十二話 「融解3」 2013.11.26