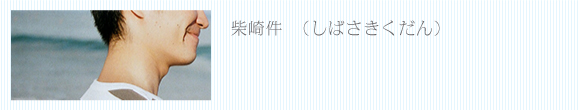![]()

2013.06.25
第二話 「記憶の羅列」
タンノが動かなくなった後も、彼の足元の川は流れ続けた。
その空間は白い床と白い天井だけがあって、他には何も存在しなかった。床は動物の皮を鞣(なめ)したような質感で、鈍い柔らかさとあたたかさがあり、巨大な生物の背中に乗っているような感覚があった。空には雨が降り出す直前の雲を固めたみたいな重い光があった。白い川と同じように、どこかに電源がついていそうな人工的な光だった。
彼が眠った(正確には動かなくなった)後、川の幅は徐々に狭くなり、ぼんやりとしか見えなかった対岸がはっきりと目にすることができた。
静止したタンノの鼻からは、わずかな呼吸が漏れ続けている。
タンノは目を閉じたまま、いろいろな景色を見た。夢を見るというよりも、想像の世界にそのまま入っていくような、奇妙な感覚だった。
景色のほとんどは、どれも見覚えのあるものだった。それらは、タンノの記憶から復元されたものだった。
これが走馬灯というものか、と彼は思う。
次々と現れる見覚えのあるシーンは、特急の列車の窓を眺めているみたいに、目に入った次の瞬間にはすでに違う景色に変わっていた。懐かしさや切なさや、その記憶に付随する別の記憶などが発生する前に、新しい再会が連続していった。
何も考えずに記憶の羅列を眺めていると、勢いを失ったルーレットがゆっくりと速度を落としていくみたいに景色の移り変わる速度が遅くなり、やがて一つの記憶に留まった。
生まれたばかりの子猫を拾ったときの記憶だ。
タンノが十一歳の時の下校途中だった。九月の終わりの頃で、まだ夏の暑さが空気に染み付いていたが、日没は早く薄暗い夕暮れだった。
電柱の脇に不自然に置かれた黒いゴミ袋から、具合の悪い窓を開けるような、キィキィという声が聞こえた。タンノは通り過ぎようとしたが、その声に含まれた救いを求める叫びを無視することができず、ゴミ袋の前で立ち止まった。足のつま先で軽く小突くと、今度ははっきりとした声でキィキィと鳴いているのが聞こえた。
周りを見ても自分以外に人影はなかった。
一体、どういう種類の人間がこういうことをするのだろう、と思いながら乱雑に結ばれた口をほどいた。中を覗くと、トイレットペーパーが敷き詰められた中に、骨と皮でできた二つの塊がこまかく震えているのが見えた。湿っている体毛とまだ開いていない目を見て、宇宙人みたいだ、とタンノは思った。一匹は震えて鳴いていたが、もう一匹は眠っているのか死んでいるのか身を固くして動かなかった。
タンノはゴミ袋を抱えたまま急ぎ足で家路に就いた。家に到着する頃には、ほとんど全力疾走に近い速度で走っていた。運んでいるとき、トイレットペーパーのこすれる音とかすかな子猫の声がずっと鳴り止まなかった。
彼は玄関に着くと母親を呼んで、猫を拾ったことと助けてやりたいということを伝えた。どういうわけか、それを拾ったのは何かの運命で、自分はこの猫を助けるヒーローなのだと思い込んでいた。その猫達とこれから何年も一緒に過ごしていくビジョンまで、いつの間にか頭の中にできていた。
訝しげな顔をしながら、見せてみなさい、と母親は言った。タンノが猫の入ったゴミ袋を渡し、母親は中を覗く。中にいる猫を見た瞬間、想像していた姿とは違うグロテスクな塊に驚いて母親は悲鳴を上げて手を離し、袋ごと落としてしまった。コンクリートに落下したふたつのやわらかい体は、それで死んでしまった。タンノは怒りと少しの悲しみで一晩中泣き叫んだ。彼がそれほどまでに怒ったのは、後にも先にもこの一度だけだった。
ひどいよなぁ、とタンノは記憶の前でぽつりとつぶやいた。
その後も、走馬灯は速度をあげて続いたが、眺めることができたのはその記憶だけだった。
記憶がもし最後まで続いてるのであれば、自分が誰に、何故刺されたのかわかるのかもしれない、と思ったが、そのシーンは目にすることができなかった。
新しい記憶ほど、靄がかかっているように見えた。
タンノは再び、夢の中で目を覚ました。天井の鈍いまぶしさがまぶたをすり抜けて染み込んでくる。
川の対岸が近くなってることに気付き、その向こうに誰かが立っているのが見えた。目を細めて男の顔を確認すると、タンノは反射的に手を上げた。
「ひさしぶり」
十年ぶりに会う友人の顔を見ながら、これ、ほんとに三途の川なんだな、と彼は思った。
(続)